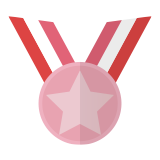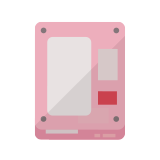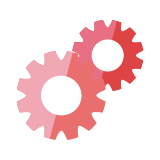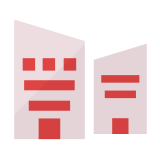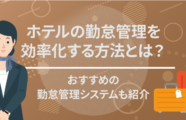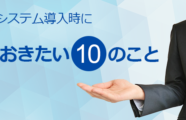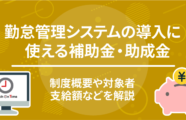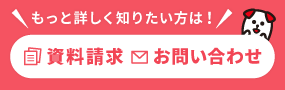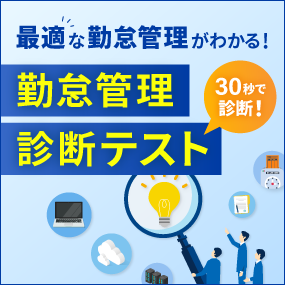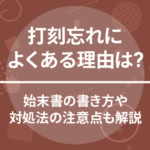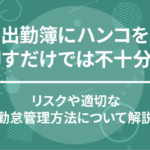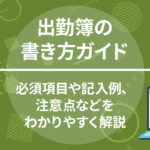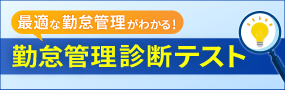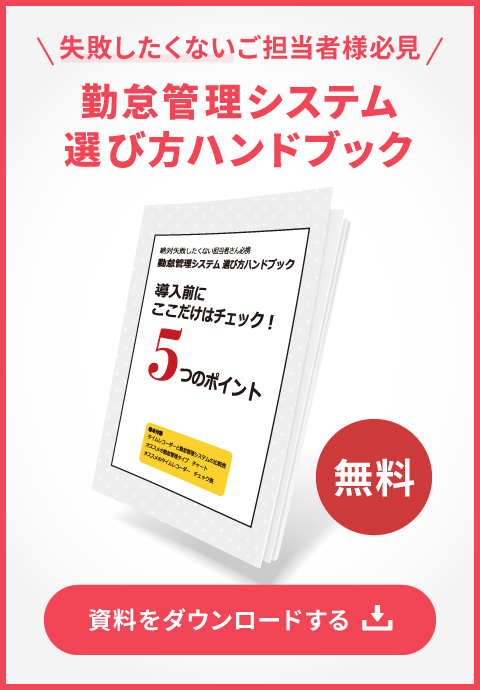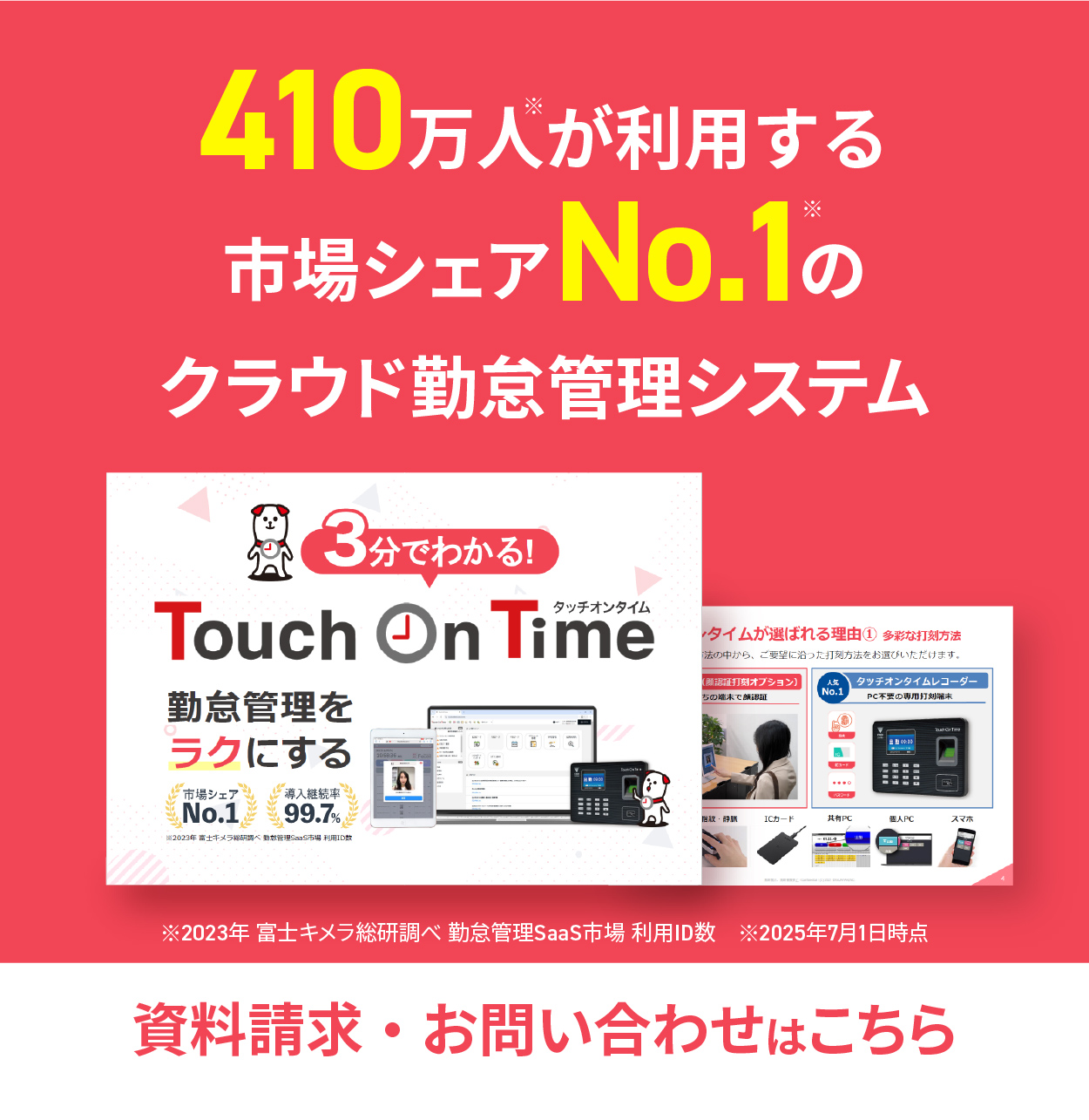打刻忘れによくある理由は?始末書の書き方や対処法の注意点も解説
勤怠管理システム
打刻
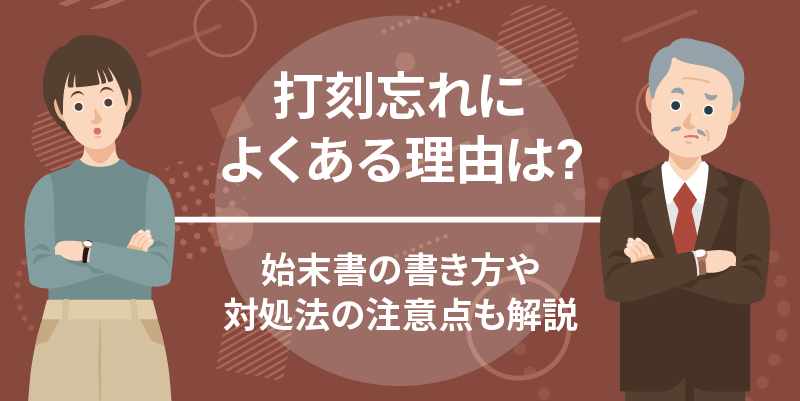
公開日:2025年10月24日
こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。
出勤や退勤の打刻をうっかり忘れることは、どの職場でも起こり得る問題です。しかし、勤怠管理における打刻忘れは労働時間の把握や給与計算に影響を与え、場合によっては始末書の提出が必要となることもあります。
この記事では、打刻忘れによくある理由や始末書の書き方、さらに対処法の注意点、防止のための工夫について分かりやすく解説します。
- 打刻忘れによくある理由と起こりやすい職場環境
- 打刻漏れがもたらすリスクと企業への影響
- 打刻忘れ時の正しい対処法と始末書の書き方
- 再発を防ぐための仕組みづくりとシステム活用
打刻忘れによくある理由
打刻忘れが発生する理由は、従業員の習慣や職場環境、システム面の問題などさまざまです。原因を正しく理解することで、再発を防ぎやすくなります。
打刻する習慣がない
従業員にとってタイムカードの打刻が日常的な行動になっていないと、つい忘れることがあります。打刻が、労働時間の記録や勤怠管理に直結する大切な作業だという認識が薄い場合も珍しくありません。
そのため、企業側は定期的に打刻の意味を伝えたり、忘れた場合はどのようなリスクがあるのかを説明したりして、全員に確実な打刻を徹底させることが重要です。
打刻する場所が目につきにくい
打刻忘れの従業員が多い場合、原因の1つに打刻する場所の悪さが考えられます。出勤や退勤の際に自然と目に入らない位置にタイムレコーダーが置かれていたり、席に着くまでに遠回りしなければならない場所にあったりすると、つい打刻を後回しにして忘れることが増えます。
日常的な打刻忘れを防ぐには、導線を意識した場所にタイムレコーダーを設置する工夫が必要です。
従業員ごとに始業・終業時間が異なる
従業員ごとに始業・終業時間が異なる職場では、打刻を忘れるケースが目立ちます。シフト勤務やフレックスタイム制のほか、早出や残業、休日出勤など普段と違う働き方になると、つい打刻を忘れがちです。
さらに外回りや出張による直行直帰も、始業・終業時間が従業員ごとにバラバラになりやすく、打刻忘れが増える要因になります。多様な勤務形態に対応するためには、打刻のルールを明確に決める必要があります。
システムに不具合が起きている
打刻漏れはシステムの不具合によっても発生します。よくあるのがICカードが反応しない、アプリが固まって操作できない、通信エラーで記録が反映されないといったトラブルです。
また、タイムレコーダーの印字が擦れて時刻などを判別できないケース、内部の時刻設定がずれていて打刻時間が正しく記録されないケースも打刻忘れ扱いになることがあります。システムに不具合がある際は、速やかに修理や調整を行うことが重要です。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
打刻忘れによって発生するリスク
打刻忘れが続くと、勤怠管理の精度が下がり、企業にさまざまな影響を及ぼします。特に労働時間の把握や給与計算に直結するため、トラブルの原因になりやすい点に注意が必要です。
正確な労働時間を把握できない
企業には、労働安全衛生法第66条の8の3に基づき、従業員の正確な労働時間を把握・管理する義務があります。しかし、打刻忘れが生じると、従業員が実際に働いた時間を正確に把握できません。
なお、労働時間には、上司から明示的に指示を受けて業務を行う時間だけでなく、黙示的に対応を求められている時間も含まれます。そのため、打刻漏れによって記録が抜け落ちると、見かけの勤務時間と実際の労働時間にずれが生じ、管理体制の不備や労務トラブルにつながるおそれがあります。
※参考:労働安全衛生法第66条の8の3|e-Gov法令検索
人事・労務の負担が増える
打刻忘れが発生すると、人事や労務の担当者は従業員に実際の勤務時間を確認し、記録を修正して集計し直す必要があります。パートなどの非正規雇用が多い職場では、確認作業だけで膨大な時間がかかり、担当者の負担の増加は避けられません。
また、本人や上司への聞き取りは時間が経つほど正確性が失われやすく、結果として余計な労力を割かざるを得ない状況につながります。
未払いの賃金を請求される
打刻忘れは、未払い賃金の発生につながる恐れがあります。たとえば、残業をしていても退勤時に打刻の記録が残っていなければ、残業分の賃金が支払われないなどのケースです。
なお労働基準法第37条により、残業に対しては基本給の1.25倍以上の賃金を支払うのが義務です。違反した場合、従業員からの指摘や告発によって労働基準監督署から指導を受けたり、労働審判や裁判へ発展したりする可能性もあります。
※参考:労働基準法第37条|e-Gov法令検索
企業の評判低下につながる
打刻忘れが原因で賃金の未払いが発生すると、従業員から法的措置を取られる恐れがあります。さらに、SNSの利用が多い現在では従業員による企業への不満を記載した投稿が広がり、企業の信用を損なうリスクも否めません。
場合によっては労働基準監督署の調査や行政処分が入り、企業名が公表されてメディアで報道される可能性もあります。
法律違反のリスクがある
労働基準法第36条4項により、従業員の時間外労働は月45時間・年360時間が上限です。打刻忘れが繰り返されると、実際の労働時間を把握できず、気づかぬうちに基準を超えた労働をさせている危険性があります。
このような状況は法律違反に直結し、労働基準法第119条によって「6か月以下の拘禁刑」や「30万円以下の罰金」が科される可能性もあります。
※参考:労働基準法第36条4項|e-Gov法令検索
※参考:労働基準法第119条|e-Gov法令検索
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
打刻を忘れた場合の対処法
打刻忘れが起きた場合、そのまま放置すると勤怠管理に支障が出ます。以下の対処法を押さえておきましょう。
タイムカードを修正する
打刻忘れが発生した場合、実際の勤務時間を正しく把握して給与計算に反映させることが欠かせません。タイムカードの記録と実際の労働時間に差があるかを確認し、従業員本人に事実を確認する必要があります。
同僚や上司など勤務を証明できる人にも確認を取って、正確な勤怠記録として修正することが重要です。
ペナルティを科す
打刻忘れが多い従業員に対して、勤務態度を正す目的で減給などのペナルティを設けることは可能です。減給の上限額は労働基準法第91条で定められています。
しかし、打刻忘れだけを理由に減給すると、労働基準法第16条に違反するおそれがあり、基本的には避けるべき対応です。ペナルティを検討する場合は、法的な制限や運用上の注意点を十分に確認する必要があります。
※参考:労働基準法第91条|e-Gov法令検索
※参考:労働基準法第16条|e-Gov法令検索
始末書を提出させる
打刻忘れを繰り返す従業員に対しては、再発防止のために始末書の提出を求めることが可能です。始末書を書かせることで、自分の行動を振り返ってもらうきっかけになります。
ただし、1度の打刻忘れで直ちに始末書を要求すると過剰と受け取られ、従業員のモチベーションが下がる可能性もあるため、繰り返しや悪質なケースに限って実施することが重要です。
打刻忘れの理由はどう書く?始末書の書き方
始末書は、管理側が従業員に対して正式に提出を求める書類として扱われ、社員の信頼性や職務態度を確認する重要な手段です。形式にとらわれすぎず、簡潔でありながら誠意の感じられる内容にまとめさせることが大切です。
管理者は、内容の確認にあたって「打刻忘れの事実」「理由」「反省の姿勢」「再発防止策」「お詫び」の順で整理されているかをチェックします。理由は「急な対応に追われた」「打刻の重要性を認識していなかった」など具体的に記載されていることが望ましく、あらかじめ始末書のフォーマットに記載しておくと良いでしょう。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
打刻忘れが発生した場合の注意点
打刻忘れはどの職場でも起こり得ますが、対応を誤るとトラブルにつながります。法律や社内ルールを踏まえた正しい処理が大切です。
打刻忘れの欠勤扱いは違法
打刻忘れが発生しても、該当の従業員を欠勤扱いにすることはできません。労働基準法第24条では、賃金は労働者に全額を支払うことが義務付けられています。打刻を忘れたからといって労働した時間分の賃金を支払わないのは違法です。
さらに、欠勤扱いとして日給分を差し引くことは、実質的に違約金を課しているとみなされ、労働基準法第16条に違反する恐れもあります。
※参考:労働基準法第24条|e-Gov法令検索
※参考:労働基準法第16条|e-Gov法令検索
手書きによる出退勤の記入は問題なし
手書きでの出退勤記録も、一定の条件を満たせば有効です。従業員への十分な説明と、必要に応じた勤務状況の確認の仕組みを整え、上司の承認を受けた上で本人が記入する形であれば、客観的な労働時間の把握が可能となります。
一方で、手書きは改ざんのリスクが高いため、記録の透明性と正確性を確保することが重要です。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
おすすめの打刻忘れ防止策3選
打刻忘れを防ぐには、打刻の仕組みそのものを整えることが重要です。現場の状況に合わせた方法を導入することで、ミスを大幅に減らせます。
タイムレコーダーの設置場所を工夫する
タイムレコーダーの設置場所は、打刻忘れを防ぐために重要です。目立たない場所に設置している場合、従業員がうっかり通り過ぎてしまいます。従業員全員が必ず通る出入り口や通路に置くことが大切です。
さらに、タイムレコーダーの周りに社内連絡などの掲示物を置けば、自然と目に留まり、打刻を習慣化しやすくなります。
生体認証を使用する
生体認証は、人間の身体的特徴を利用して本人確認を行う仕組みで、最近はスマートフォンのロック解除にも広く活用されています。
指紋や顔・虹彩・静脈・耳の形などを識別要素として利用するため、他人が不正に真似することが困難です。従来のIDやパスワードのように記憶しておく必要もなく、打刻に必要なICカードなどを忘れる心配もありません。
勤怠管理システムを導入する
勤怠管理システムを導入すると、従業員の注意だけに頼らず、打刻忘れを防ぎやすくなります。具体的なメリットとしては、打刻データを自動で保存・管理できるほか、打刻漏れを知らせるアラート機能や、パソコンの起動と同時に打刻される機能などが搭載されているものもあります。
こうした仕組みを活用することで、注意を繰り返しても改善しないケースでも、打刻の記録漏れを防止できます。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
まとめ
打刻忘れは労務管理に影響を及ぼし、トラブルの原因になります。正確な勤怠管理を徹底し、安心して働ける環境を整えることが大切です。再発防止には勤怠管理システムなど、便利な仕組みを活用しましょう。
勤怠管理システムを導入するなら、タッチオンタイムをぜひご検討ください。「タッチオンタイム(Touch On Time)」は、株式会社デジジャパンが提供する、市場シェアNo.1※の勤怠管理システムです。初期費用0円で月額費用は1人300円となっています。利用制限はなく、専属サポートや電話サポート費用も0円で、すべての機能を追加費用なしで活用できます。
指紋とICカード打刻が可能な独立型端末「タッチオンタイムレコーダー」やお手持ちの端末で利用できる顔認証打刻「Facee(フェイシー)」で、労働条件に影響されることなく打刻が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
※2023年 富士キメラ総研調べ 勤怠管理SaaS市場 利用ID数
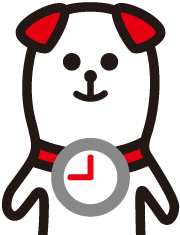
- この記事の執筆者
- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
- 受賞歴:「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」勤怠管理システム部門
ITトレンド Good Productバッジ 2022