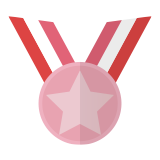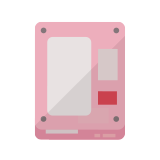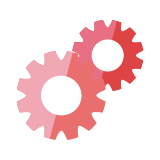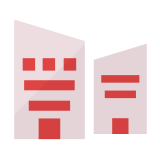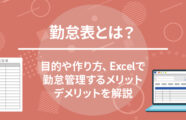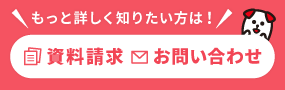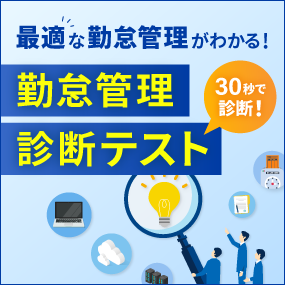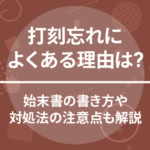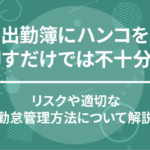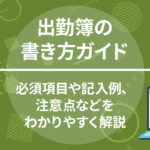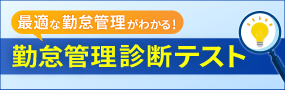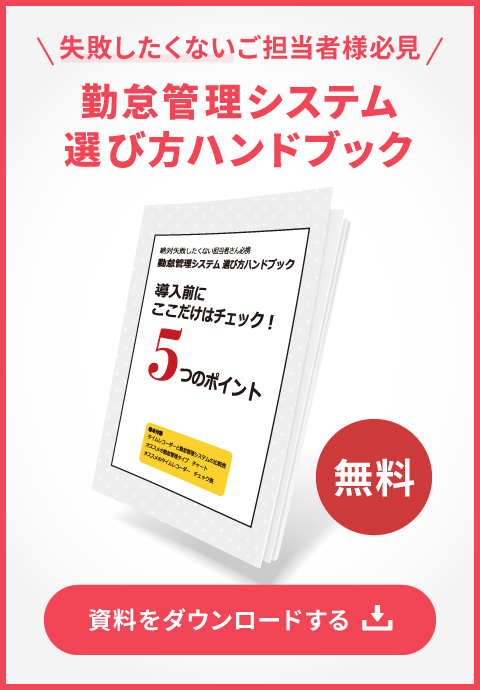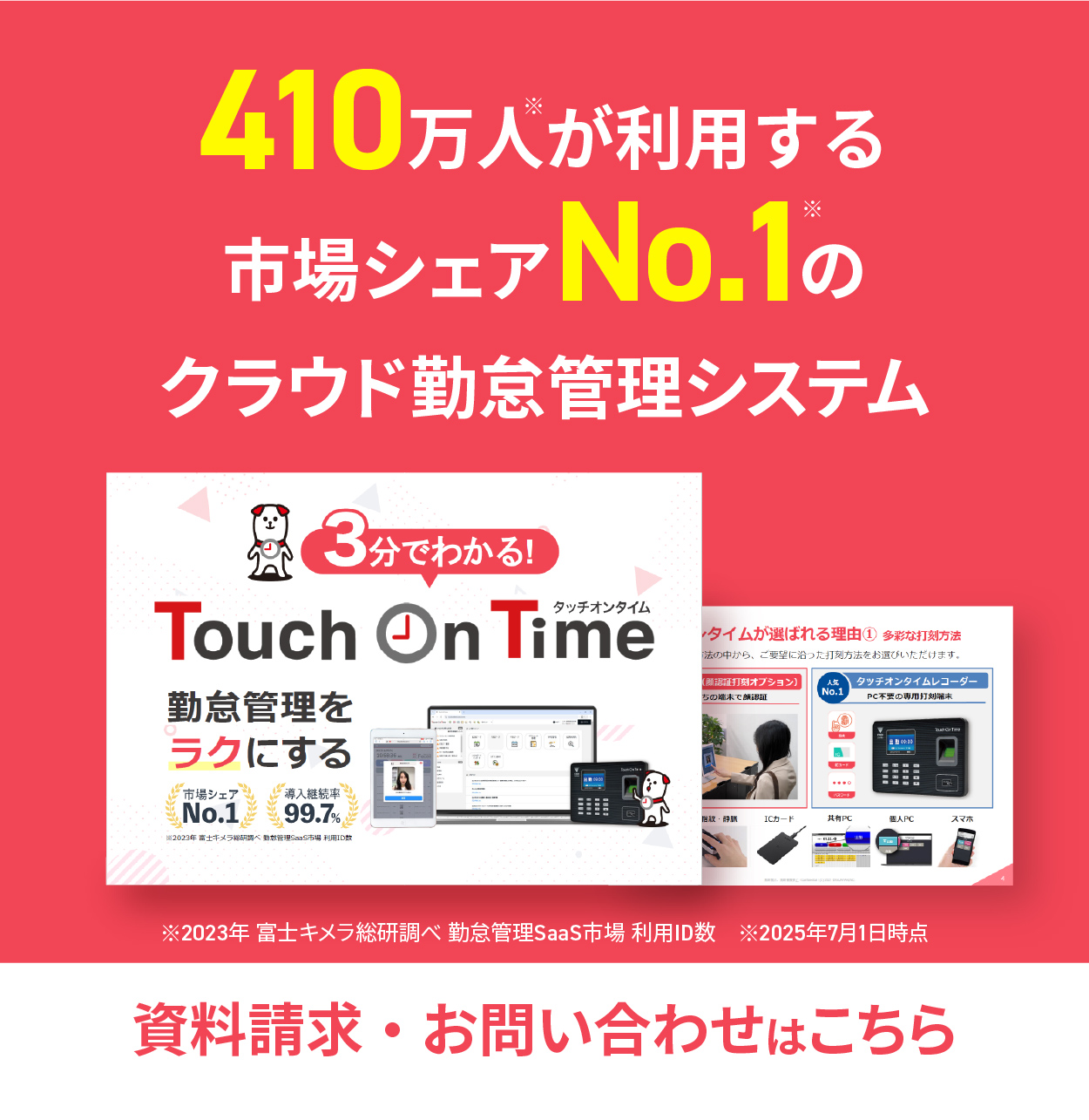勤怠管理システムの勘定科目とシステム導入時の選び方
勤怠管理システム
ナレッジ
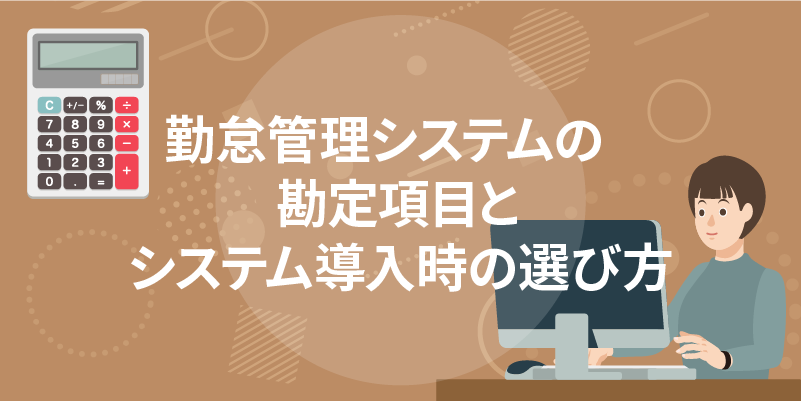
こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。
勤怠管理システムの導入時に悩むのが、費用をどの勘定科目で計上すべきかという問題でしょう。システムの種類によって適切な勘定科目が異なり、税務処理にも影響を与えます。本記事では、勤怠管理システムの勘定科目について詳しく解説し、システム選びのポイントもご紹介します。
目次
勤怠管理システムの勘定科目とは
勤怠管理システムの勘定科目は、システムの導入形態によって決まります。
勘定科目に明確なルールはない
勘定科目とは、出し入れしたお金の見出しのようなもので、支出の場合は「お金を何に使ったのか」を簡潔に表すための分類です。勘定科目には法的に明確なルールが存在せず、企業ごとに運用ルールを設定する必要があります。
ただし、税務上の適切な処理を行うため、一般的な慣例に従って設定することが重要になります。
勘定科目は一般的な決まりに則って設定する
勤怠管理システムの勘定科目設定では、システムの性質や利用形態を考慮した判断が求められます。一般的には、システムの導入形態(クラウド型かインストール型か)、取得価額(10万円未満か以上か)、使用期間(1年未満か以上か)といった要素を総合的に判断して決定しましょう。
これらの基準に基づいて、消耗品費、通信費、無形固定資産などの適切な勘定科目を選択する必要があります。
勘定科目はオンプレミス型(インストール型)とクラウド型で変わる
勤怠管理システムの勘定科目は、導入形態によって異なります。クラウド型の場合は「通信費」として処理し、オンプレミス型(インストール型)の場合は「消耗品費」として計上するのが一般的です。
この違いは、クラウド型がインターネット経由でサービスを利用する形態であるのに対し、オンプレミス型(インストール型)は自社にソフトウェアを導入する形態であることに起因します。
タイムレコーダーなどの機器は減価償却の対象
タイムレコーダーやその他の勤怠管理機器は、取得価額が10万円以上の場合、減価償却の対象となります。タイムレコーダーの法定耐用年数は5年とされており、パソコンやタブレットをタイムレコーダーとして使用する場合は4年となります。
使用可能期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは消耗品として計上できますが、それ以外は固定資産として資産計上し、耐用年数にわたって減価償却を行いましょう。
システム形態で減価償却の対象が異なる
システム形態によって減価償却の取扱いが変わります。取得価額10万円以上の場合、パソコンやデバイス機器は有形固定資産、OSやソフトウェアは無形固定資産として処理しましょう。
クラウド型システムの場合は月額利用料として毎月の費用で計上できるため、減価償却の必要はありませんが、導入時のカスタマイズ費用は無形固定資産として扱われる場合があります。
オンプレミス型(インストール型)勤怠管理システムの勘定科目
オンプレミス型(インストール型)勤怠管理システムの勘定科目は消耗品費が基本となります。詳細は以下の通りです。
オンプレミス型(インストール型)は「消耗品費」が一般的
オンプレミス型(インストール型)勤怠管理システムは、ソフトウェアを購入して自社のパソコンにインストールして使用する買い切り型のシステムです。一度購入したものを日々消耗していくという考え方であるため、仕訳は消耗品費とするのが基本となります。
オンプレミス型(インストール型)の仕訳方法
取得価額が10万円未満のオンプレミス型(インストール型)勤怠管理システムにかかる費用は、全て消耗品費として経費計上できます。ソフトウェアの購入時に、購入にかかった金額の総額を消耗品費として仕訳しましょう。
取得価額には、ソフトウェアの金額だけでなく、環境設備や人件費、インストール時に必要なカスタマイズ料も含まれる点に注意が必要です。
10万円以上は資産計上が必要
10万円以上するオンプレミス型(インストール型)の勤怠管理システムを購入する場合は、「無形固定資産」として資産計上しなければなりません。そして、減価償却の処理も必要になります。ただし、中小企業の場合は少額減価償却資産の特例を利用することで、30万円未満であれば全額を消耗品費として経費計上することが可能です。
この特例を利用する場合は減価償却は不要で、年度末の仕訳も発生しません。
クラウド型勤怠管理システムの勘定科目
クラウド型勤怠管理システムの勘定科目は通信費として計上します。
クラウド型は「通信費」が一般的
クラウド型勤怠管理システムは、インターネット経由でサービスを利用する形態であるため、「通信費」として計上するのが一般的な処理方法です。形のあるソフトウェアを購入するのではなく、インターネット上のサービスを利用することから、通信費として分類されます。
企業によっては「支払手数料」や「諸会費」として処理する場合もあり、一度決めた勘定科目は継続して使用することが重要となります。
支払いは全て経費として計上する
クラウド型勤怠管理システムにかかる支払いは、全額を経費として計上することが可能です。月額制のサブスクリプション型サービスであるため、減価償却の対象とはならず、支払った月に全額を費用として処理できます。
年間契約で一括支払いした場合でも、契約期間に応じて適切に費用配分を行うことで経費計上が認められます。
クラウド型の仕訳方法
クラウド型勤怠管理システムの仕訳は、月額利用料を支払った時点で通信費として計上します。例えば、月額5,000円のクラウド型勤怠管理システムの利用料を6月1日に支払った場合、借方に「通信費:5,000円」、貸方に「普通預金:5,000円」として記帳しましょう。
年間契約で一括支払いした場合は、前払費用として資産計上し、毎月の利用期間に応じて通信費へ振り替える処理を行います。
サポートを受けた場合の勘定科目
勤怠管理システムのサポートを受けた場合の勘定科目は、サポート内容によって異なります。システムの導入・環境整備などのサポート料は経費計上が可能で、明確なルールがないため費用の解釈によって仕訳を行います。
一般的な勘定科目としては、運営元への報酬と解釈する場合は「支払手数料」、ソフトウェアの購入費用と合わせて計上する場合は「消耗品費」、サポートのためのサービス会員費と解釈する場合は「諸会費」を使用しましょう。
勤怠管理システムの選び方
勤怠管理システムを選ぶ際は、自社の勤務形態に適したシステムを選択することが重要です。まず、自社の就業規則や勤務形態に対応できるかを確認しましょう。給与システムや人事管理システムといった基幹システムとの連携も重要で、単独でしか使えないシステムでは結局手作業が発生し、非効率となってしまいます。
また操作性については、出退勤の打刻が容易で、外回りなど従業員の勤務を鑑みて使いやすいシステムを検討する必要があります。
勤怠管理システムを導入する際の注意点
勤怠管理システムの導入を成功させるためには事前準備が重要となります。ここではいくつかの注意点を解説します。
事前に自社に必要な機能を洗い出す
勤怠管理システムの導入前には、自社の就業規則や勤務形態を詳しく把握することが必要となります。正社員や派遣従業員、パート・アルバイトが混在している場合や、変形労働制、裁量労働制といった複雑な勤務形態がある場合は、それぞれに対応できる機能があるかを確認します。
また、給与システムや人事管理システムとの連携機能も、自社のシステムに適しているかを確認しましょう。
無料トライアルがある場合は事前に試す
多くの勤怠管理システムでは無料トライアル期間が設けられており、導入前に実際の使い勝手を確認することが可能です。テスト運用を行うことで、自社の勤務形態に合うかどうか、従業員が使いやすいかどうかを事前に把握できます。
無料期間を導入の準備期間に充てることも可能で、自社に合わなければ別の勤怠管理システムに変更することも容易です。
オンプレミス型(インストール型)の変更を希望する場合は、開発元に問い合わせる
オンプレミス型(インストール型)の勤怠管理システムは買い切り型であり、一度購入すれば月額料金は不要というメリットがあります。しかし、導入後にカスタマイズが必要になった場合は、開発元に問い合わせて対応可能かどうかを確認する必要があります。
変更要望がある場合は、追加費用や対応期間についても事前に確認しておきましょう。
新規開発の場合は見積書を取得し比較する
新規開発で勤怠管理システムを構築する場合は、複数の開発会社から見積書を取得して比較検討することが重要です。初期費用は最低でも1,000万円前後からとなり、大企業が大規模システムを開発する場合は3,000万円以上となるケースもあります。
開発費は明確な基準が無いため、相見積もりを取ることで相場を把握し、各項目にかかる費用を詳細に比較することが必要となります。
勤怠管理システム導入後の確認ポイント
勤怠管理システム導入後は効果測定を必ず行いましょう。
勤怠管理にかかる工数を導入前後で比較する
勤怠管理システム導入後は、勤怠管理業務にかかる工数を導入前と比較して効果を測定することが重要です。従来の手作業による集計や確認作業が自動化されることで、人事担当者の業務負担がどの程度軽減されたかを定量的に把握しましょう。
また、従業員側の打刻や申請にかかる時間も測定対象に含めることで、組織全体での効率化効果を正確に評価できます。
有給取得率や残業時間削減率を確認する
システムによる可視化機能により、従業員の有給残日数や取得状況をリアルタイムで把握できるようになり、有給取得の促進につながるでしょう。残業時間についても、システムのアラート機能により一定時間を超過した従業員に対して早期の対応が可能となり、働き方改革の推進に役立ちます。
導入前後の数値を比較することで、システム導入による労働環境改善の効果を客観的に評価できます。
まとめ
勤怠管理システムの勘定科目は、システムの導入形態によって異なります。クラウド型は「通信費」、インストール型は「消耗品費」として計上するのが一般的で、10万円以上の場合は資産計上が必要となります。
タイムレコーダーなどの機器は減価償却の対象となり、適切な会計処理を行うことが重要です。システム選びでは、自社の勤務形態に適した機能を持つものを選択し、無料トライアルで事前に使い勝手を確認することをおすすめします。
もし勤怠管理システムにお悩みでしたら、「タッチオンタイム」をぜひお試しください。初期費用0円、月額300円/人からと導入しやすく、柔軟なシフト作成・管理機能が充実しています。また、給与計算システムとの連携により、月末の煩雑な作業も大幅に削減可能です。
電話サポートと30日間の無料トライアルもご用意しておりますので、ITが苦手な人でも安心してご利用いただけます。まずは「タッチオンタイム」の資料請求や無料トライアルで、その使いやすさと機能性をぜひご体験ください。
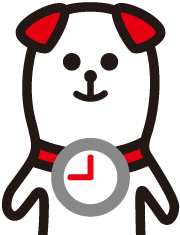
- この記事の執筆者
- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
- 受賞歴:「BOXIL SaaS AWARD Spring 2025」勤怠管理システム部門
ITトレンド Good Productバッジ 2022