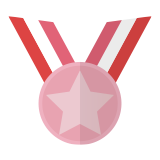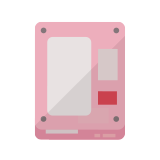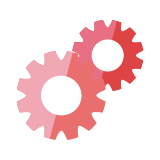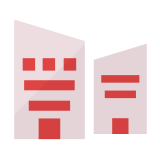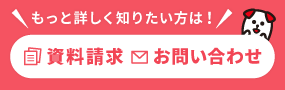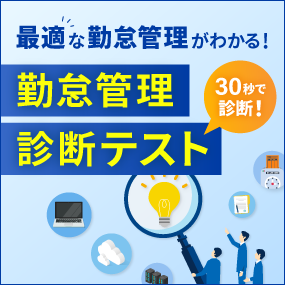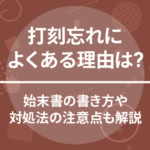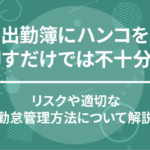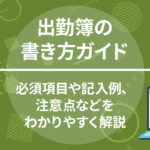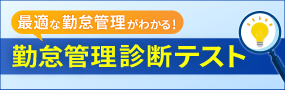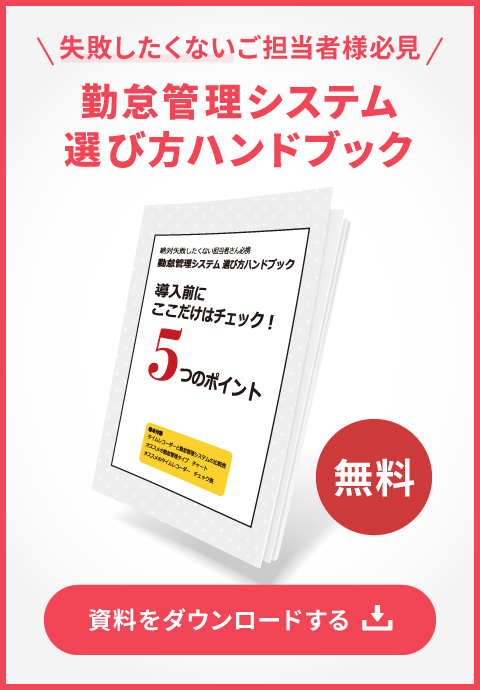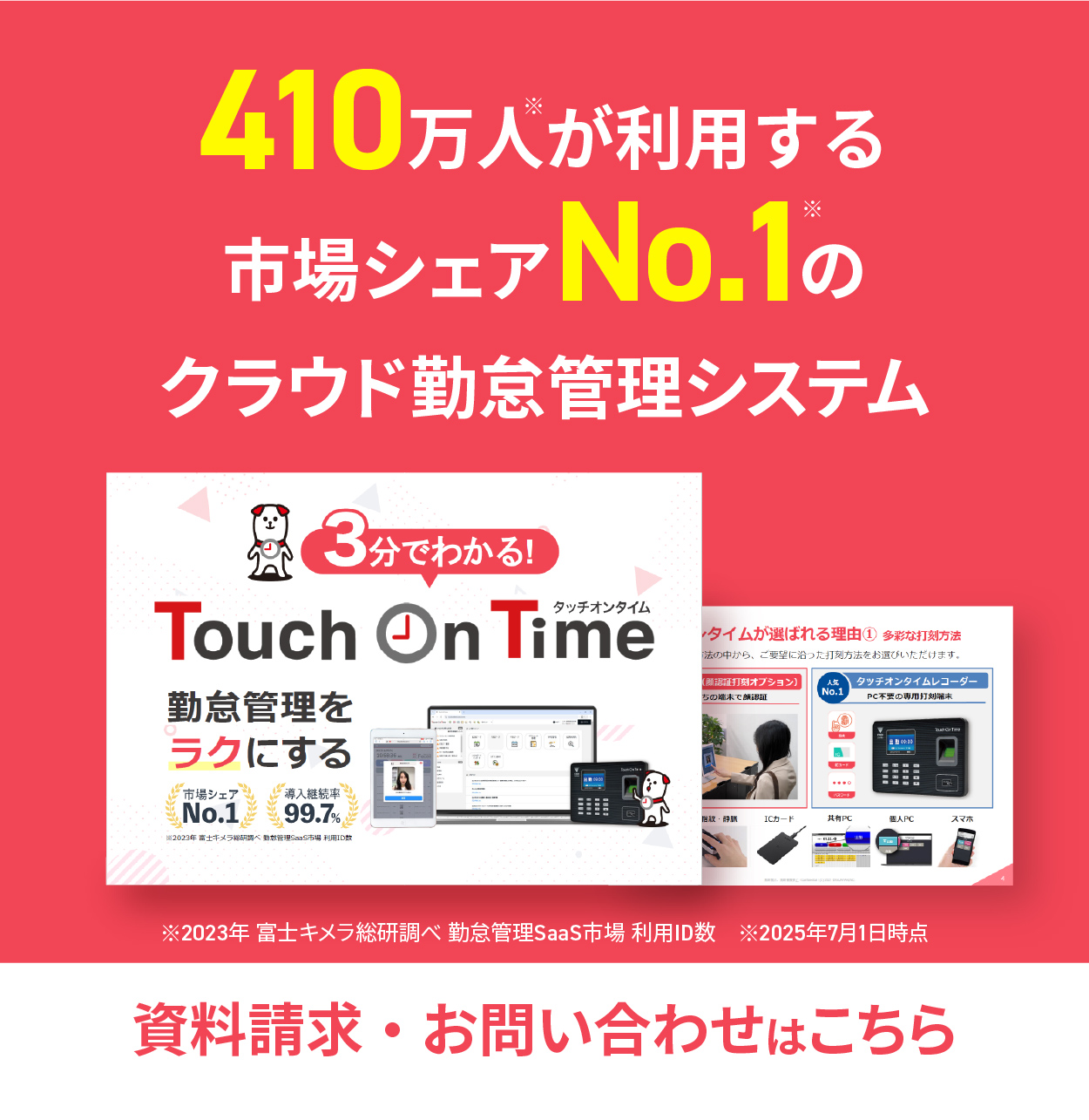勤怠管理は企業の義務?関連する法律や押さえておきたいポイントを解説
勤怠管理システム
タッチオンタイムの紹介
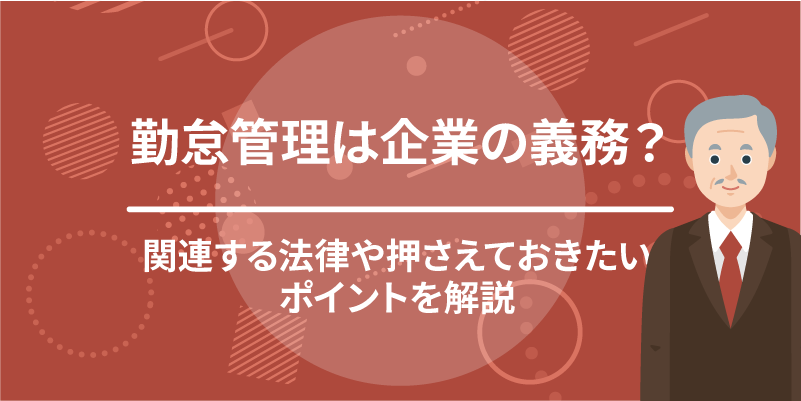
公開日:2025年7月25日
こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。
従業員の勤怠管理は、人事労務部門における重要な業務の1つです。しかし、法的義務や関連する法律については、意外に知られていないケースも多いでしょう。
そこで本記事では、勤怠管理の法的義務や関連法令について詳しく解説します。法律を順守した勤怠管理のポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- 勤怠管理が企業にとって法的義務である理由と、関連する労働基準法の概要
- 客観的な労働時間把握や自己申告制の制限など、ガイドラインに基づく管理の実務ポイント
- 労働時間・休憩・休日・有給・割増賃金など、勤怠管理に関わる具体的な法規制の内容
- 派遣・パート・アルバイトなど多様な雇用形態に応じた勤怠管理の注意点と対応方法
- 法令順守と業務効率化を同時に実現するための勤怠管理システム活用の有効性
目次
勤怠管理は法律で定められた企業の義務
従業員の勤怠管理は、法律によって定められた企業の義務です。
労働基準法では1日・1週間単位での労働時間の上限が定められており、これを超える労働を依頼する場合には、従業員と労使協定を締結しなければなりません。こうした労働時間に関する法律を守るためにも、従業員の勤怠管理は必須といえます。
勤怠管理のおもな目的
勤怠管理のおもな目的は、「労働者の保護」と「労使間のトラブル防止」の2点です。
勤怠管理が適切に行われず長時間労働が常態化すると、労働者の心身の影響に悪影響が及ぶ恐れがあります。過重労働は最悪の場合、過労死の原因にもなりかねないため、企業には労働時間の厳格な管理が義務付けられています。
また、多くの場合、従業員への給与は労働時間に基づいて計算されるものです。給与や健康被害を巡る労使間のトラブルを避けるためにも、企業は法律に基づき勤怠情報を管理しなければなりません。
勤怠管理の義務を果たさない場合の罰則
従業員の労働時間を正確に把握できなくても、そのこと自体に罰則が科されることはありません。しかし、勤怠管理を怠ったことにより法律で定められた労働時間を超過した場合は、罰則の対象になる恐れがあります。
例えば、時間外労働の上限規制に違反した場合の罰則は、6か月以上の懲役または30万円以下の罰金です。また、法律のルールに基づき有給休暇を取得させなかった場合には、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
勤怠管理の必要がない労働者
基本的に、勤怠管理は全ての労働者に対して必要です。ただし、一部例外も設けられています。例えば、農業や水産業などは事業が天候に左右されやすいことなどから、労働者の勤怠管理は不要です。
また、経営者と一体となって従業員の労務管理などを行う人や、みなし労働時間制で働く労働者についても、企業に勤怠管理の義務は適用されません。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
労働時間の客観的把握の義務について
ここでは、厚生労働省の定める「労働時間の客観的把握」の定義や、注意点などを解説します。
タイムカードなどの客観的な記録方法が義務化
2017年、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定されました。これにより、労働時間をタイムカードやICカード、パソコンの使用時間などの記録から、客観的に把握することが義務化されました。
※参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
自己申告制は原則禁止
先述したガイドラインの策定により、従業員の自己申告に基づく勤怠管理は原則禁止されています。しかし、取引先からの直行直帰で、社外から勤怠管理システムにアクセスできないような場合に限り、以下の措置を講じることで自己申告制が認められます。
なお、その場合も「従業員や管理者の周知」「実際の労働時間との乖離(かいり)の補正」など、いくつかの措置を講じる必要があるので注意が必要です。詳しくは、厚生労働省のガイドラインで確認してください。
※参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
賃金台帳の適正な調製が必要
ガイドラインにおいて使用者が講じるべき措置には、賃金台帳の調製も含まれます。企業は、従業員ごとに労働日数・労働時間・時間外労働時間・深夜労働時間・休日労働時間などの項目を適正に記入しなければなりません。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
勤怠管理に関連する労働基準法での規定
ここからは、労働基準法のなかから、勤怠管理に関係のある規定を紹介します。
法定労働時間と所定労働時間
労働基準法第32条により、企業は従業員に対して「1日8時間・週40時間」を超える労働をさせてはならないと定められています。これを「法定労働時間」といい、従業員に法定労働時間を超える労働を依頼する場合には、「時間外・休日労働に関する協定(以下、36協定)」の締結が必要です。
一方、「所定労働時間」とは始業時間から終業時間までの労働時間(休憩時間を除く)のことで、法定労働時間を超えないよう設定しなければなりません。
休憩と休日
労働基準法第34条では、従業員に与える休憩について以下のように定められています。
| 労働時間 | 休憩時間(下限) |
|---|---|
| 6時間超 | 45分間 |
| 8時間超 | 1時間 |
加えて、休憩時間は「労働時間の途中で、一斉に、自由時間として」付与することが原則です。
また、労働基準法第35条により、企業は従業員に対して少なくとも「週1日または4週を通じて4日」の休日を与えなければならないと定められています。
時間外労働の上限規制
36協定を締結すれば法定労働時間を超えた労働が可能ですが、もちろん、従業員を無限に働かせられるわけではありません。法定労働時間を超える「時間外労働」は、原則として「月45時間・年360時間」までと定められています。
「特別条項付き36協定」を結べば上記を超えて労働できますが、その場合も以下を守らなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が1か月平均80時間以内
- 月45時間を超える労働は年6か月まで
2024年4月以降は猶予期間が終了
時間外労働の上限規制は、運送業のドライバーや医師などの一部業種に限って猶予期間が設けられていました。しかし、2024年4月に猶予期間が終了し、現在は条件付きで全ての業種に適用されています。
年5日の年次有給休暇の取得義務
労働基準法第39条第7項により、企業は年10日以上の有給休暇を付与する従業員について、年5日の有給休暇を取得させなければならないと定められています。
なお、年10日以上の有給休暇を付与する必要がある従業員の条件は、以下の通りです。
- 雇用から6か月以上継続して勤務している
- 雇用から6か月間の全労働日の8割以上出勤している
時間外労働に対する割増賃金
労働基準法第37条の規定では、時間外労働には25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
なお、法改正により、時間外労働が月60時間を超えた分については、50%以上の割増賃金が必要となりました。また、法定休日の労働には35%以上、深夜労働(22時から翌5時まで)には25%以上の割増賃金が適用されます。
2023年4月以降は中小企業も引き上げの対象に
時間外労働が月60時間を超える場合の割増賃金の引き上げは、当初は大企業のみを対象としたものでした。しかし、2023年4月以降は中小企業も引き上げの対象となっており、同じルールに基づいて割増賃金を支払う必要があります。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
2025年以降の勤怠管理に関連する法改正
ここでは、2025年以降の勤怠管理に関わる法改正について紹介します。
育児・介護休業法の改正
育児・介護休業法は2024年に改正され、2025年4月から段階的な施行がスタートしました。勤怠管理に関連する改正点は、おもに以下の通りです。
- 子どもの看護休暇の対象となる子どもが、未就学児から小学校3年生まで拡大
- 残業免除の対象が「3歳未満の子どもを養育する人」から「未就学児を養育する人」へ拡大
- 3歳未満の子どもを養育する従業員が、育児のためのテレワークを選択できるよう、企業に努力義務が課される
- 勤続期間6か月未満でも、介護休暇の取得が可能になった
- 家族の介護のためのテレワークを選択できるよう、企業に努力義務が課される
14日以上の連続勤務の禁止
現行法では最長48日間の連続勤務が可能ですが、これを是正し、14日以上の連続勤務を禁止する方向性で検討が重ねられています。法改正のタイミングは2026年とみられていますが、具体的な時期は決まっていません。
影響のある業種はそれほど多くないでしょう。しかし、連続勤務日数が多い企業は注意が必要です。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
【就業形態別】勤怠管理における注意点
正規雇用以外の就業形態として、派遣労働者とアルバイト・パートなどがあります。ここでは就業形態別に勤怠管理の注意点を解説します。
派遣労働者の勤怠管理
派遣労働者の勤怠管理は、派遣元(人材派遣会社)と派遣先の双方で必要です。それぞれの管理項目を把握し、派遣元と連携しながら勤怠管理を行ってください。
| 管理項目 | |
|---|---|
| 派遣元 | ・給与支給 ・有給休暇 ・時間外労働、割増賃金 など |
| 派遣先 | ・労働時間 ・休憩、休日 ・深夜労働 ・労働環境の整備 など |
派遣先は派遣労働者とは直接的な雇用関係にはありませんが、自社の従業員と同様、労働時間や休憩などを適正に管理し、安心して働ける環境を整えることが大切です。
アルバイト・パート従業員の勤怠管理
アルバイト・パート従業員の勤怠管理におけるポイントは、正規雇用の従業員と変わりません。法定労働時間や時間外労働、割増賃金などの規定は、雇用形態にかかわらず適用されます。
たとえば、アルバイトやパートでも「入社から6カ月以上経過し、出勤率が8割以上」の場合は有給休暇を付与する義務があり、1日8時間・週40時間を超えた労働に対しては残業手当の支払いが必要です。また、法定休日に勤務した場合には、所定の割増率で休日手当を支払う必要があります。賃金計算は1分単位で行い、曖昧な切り捨ては認められません。
非正規雇用だからといって法律の対象外にはならないため、各種ルールに従ったうえで勤怠管理をすることが重要です。ただし、アルバイト・パート従業員はシフト勤務による時給制で働くケースが多いため、勤怠管理が複雑になりがちです。勤怠管理システムを導入するなどして、業務の効率と正確性の向上を図るとよいでしょう。
勤怠管理の法的ルールを順守するためのポイント
勤怠管理の法的ルールを守るためのポイントを3つ紹介します。
労働時間は1分単位で管理する
労働基準法第24条により、賃金はその全額を従業員に支給しなければならないと定められています。そのため、従業員の労働時間は、1分単位で正確に把握することが大切です。
例えば、10分の遅刻を15分に切り上げたり、労働時間を30分単位で管理したりすることは違法となります。
朝礼や着替えも労働時間に含まれる場合がある
「労働時間=業務を行っている時間」と思われがちですが、場合によっては朝礼や着替えの時間なども労働時間に含まれることもあります。基本的には、朝礼や着替えが上司の指示によるものである場合は、労働時間に含まれる可能性が高いでしょう。
一方、従業員が自分の意思で仕事着に着替える場合などは、労働時間には含まれません。
出勤簿は5年間保存する
従業員の出退勤時刻や出勤日などを記録した出勤簿は、賃金台帳や労働者名簿と同じ「法定三帳簿」の1つです。出勤簿は、法律により5年間の保存が義務付けられています。
現在は経過措置期間中であるため、保存期間は3年でも問題ありませんが、経過措置がいつ終了してもよいように準備しておきましょう。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
勤怠管理システムの活用で人事労務の負担を軽減
手書きの出勤簿やExcelを使った勤怠管理は、厚生労働省のガイドラインでも推奨されていません。ガイドラインを順守して適正に勤怠管理を行えるよう、勤怠管理システムの導入をおすすめします。
勤怠管理システムは、ICカードや位置情報など多様な打刻方法に対応した製品が多く、客観的な記録による勤怠管理を実現します。また、勤怠情報の集計・管理を自動化できるため、担当者の負担も大幅に軽減されるでしょう。
まとめ
従業員の勤怠管理は、法律によって定められた義務です。企業は、労働時間や休憩、休日などに関連する各種法令を守りながら、従業員の労働時間を客観的に把握する必要があります。
法令順守と業務効率化を両立するなら、勤怠管理システムがおすすめです。クラウド型勤怠管理システム「タッチオンタイム」は、市場シェアNo.1※の実績があります。初期費用はかからず、月額300円/人から手軽に導入できるのが魅力です。
また、パソコンやスマートフォンに加えて、指紋やICカードで打刻できる専用端末や、顔認証に対応した「Facee」など、さまざまな就労環境に応じた打刻方法を提供しています。
さらに、30日間の無料トライアルや手厚い電話サポートがあるため、ITに不慣れな人でも安心して利用を始められます。お気軽にご相談ください。
※2023年 富士キメラ総研調べ 勤怠管理SaaS市場 利用ID数
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
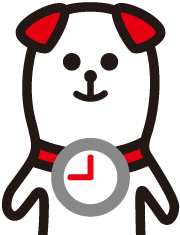
- この記事の執筆者
- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
- 受賞歴:「BOXIL SaaS AWARD Spring 2025」勤怠管理システム部門
ITトレンド Good Productバッジ 2022