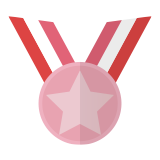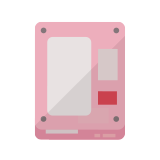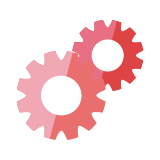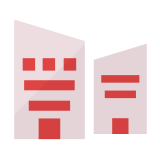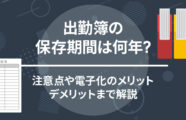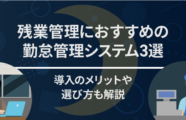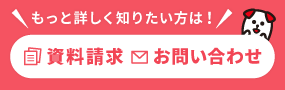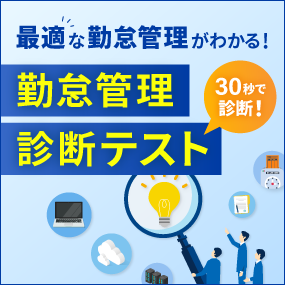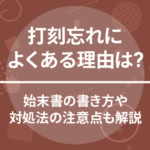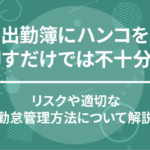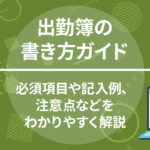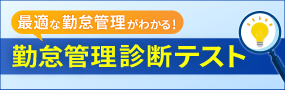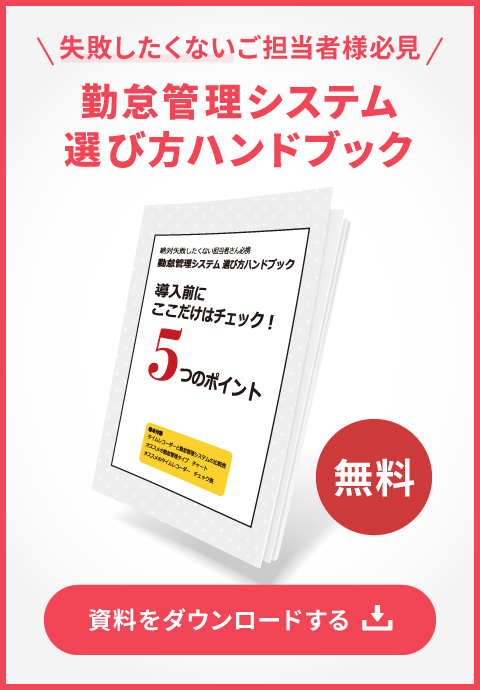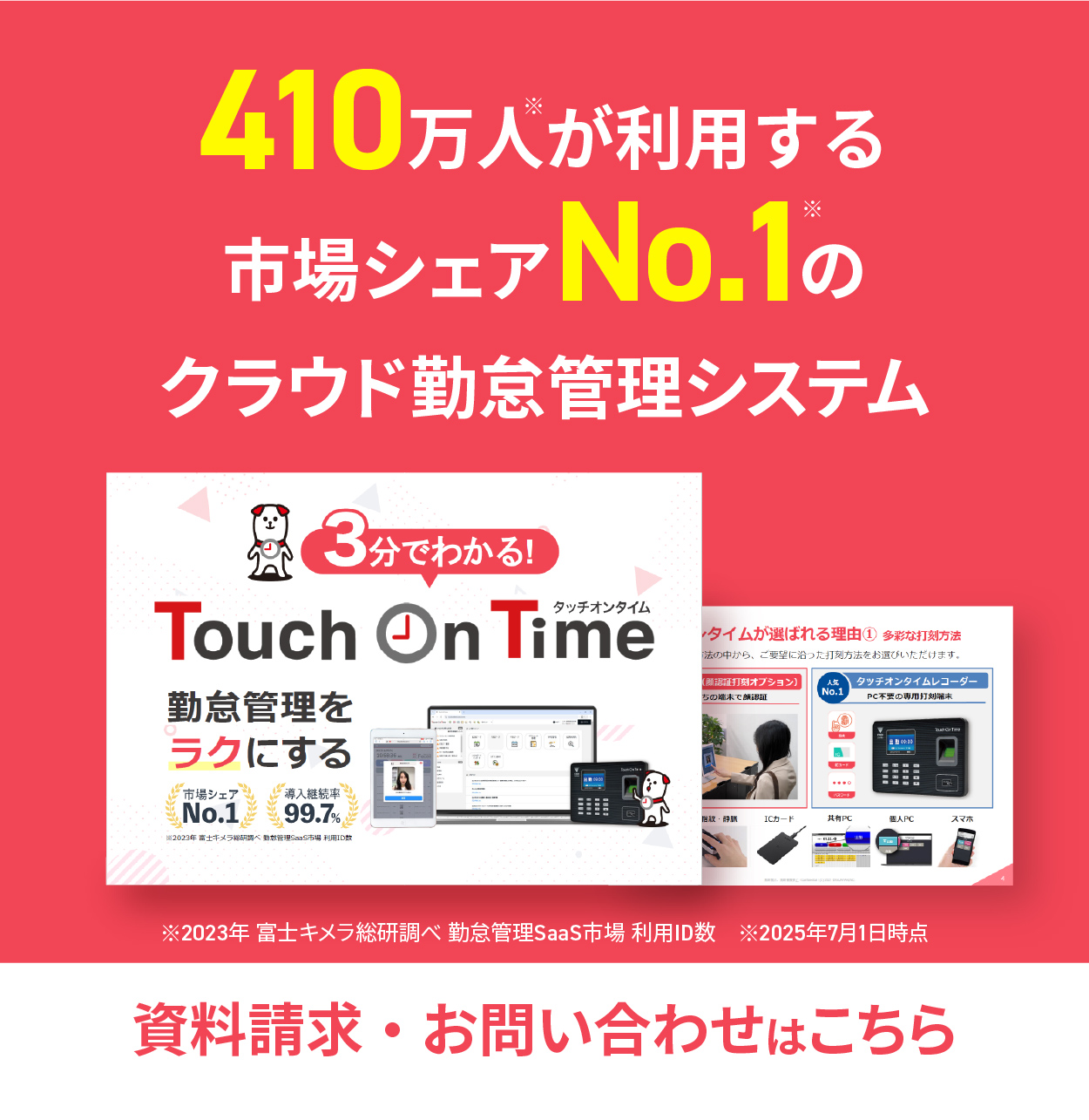タイムカードで打刻を行う際の課題は?勤怠管理システムの特徴についても解説
勤怠管理システム
働き方改革
打刻
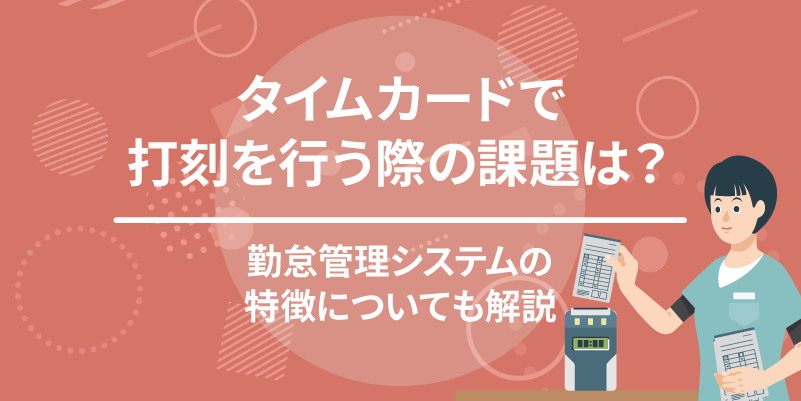
公開日:2025年9月18日
こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。
働き方改革への対応を目指し、タイムカードによる勤怠管理を脱却して勤怠管理の効率化を図りたいと考えている担当者もいるでしょう。本記事では、タイムカードによる打刻の課題や打刻タイミングなどについて解説しています。業務の効率化が実現できる勤怠管理システムの特徴についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- 打刻が必要な理由と法的な背景
- タイムカード運用時の打刻タイミングやルールの整理
- タイムカードの課題と改善のための視点
- 勤怠管理システムによる効率化のポイント
目次
打刻とは
打刻とは、従業員が出勤や退勤、休憩などの時間を記録するための行為です。従来はタイムカードを機械に差し込み、時刻を印字する方法のことを指していました。
現在では、パソコンやスマートフォンを利用した勤怠管理システムによる打刻も普及しています。これにより勤務時間の記録が自動化され、給与計算や残業管理、シフト管理などの業務も効率化されるようになりました。
打刻が必要な理由
打刻が必要な理由について、該当する労働基準法に触れながら解説します。
給与を正しく支払うため
給与は従業員の労働時間をもとに算出されるため、給与を正しく支払う意味合いから打刻が必要です。打刻によって出勤・退勤時刻や休憩時間を正しく記録すれば、残業代や深夜手当などを含めた正確な給与計算が可能になります。
労働時間を管理するため
打刻が必要な理由は、労働時間を管理するためです。労働基準法第32条などによって、企業には従業員の労働時間を適切に管理する義務が定められています。打刻を通して勤務時間を正確に把握すれば、過重労働の防止や労働時間の上限規制への対応が可能になるでしょう。
また、休憩や休日の取得状況を把握できるため、従業員の健康管理や労働環境の改善にもつながります。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
打刻ルールの明確化が必要な理由
打刻は労働時間を正しく記録するための重要な手段です。しかし、従業員の判断に任せると「出社直後に打刻するのか」「着替え後に打刻するのか」などでばらつきが生まれ、不公平な労働時間管理につながります。
さらに、2019年4月に施行された労働安全衛生法の改正により、企業には客観的な記録で労働時間を把握する義務があります。この義務を果たすためにも、打刻のタイミングや方法を具体的に定めた明確なルールの策定が不可欠です。
タイムカードの打刻タイミング
ここでは、タイムカードの打刻タイミングについて解説します。適切なタイミングで打刻ができているか判断する参考にしてください。
出勤時
出勤時は、実際に業務を開始する直前に打刻する必要があります。早く出社しても業務を始めていなければ、その時間は労働時間として扱われません。ただし、着替えや朝礼の時間は労働時間に含まれるため、着替え・朝礼は打刻後に行うようにしましょう。
休憩時
休憩に入る際と業務再開時の打刻は、法律上義務とはなっていません。しかし、企業は従業員に休憩を取らせる義務を負っています。そのため、適切に休憩を取らせ、かつ労働時間を正確に把握するためには、休憩時間の打刻が必要といえます。
退勤時
退勤時は、その日の業務を終えた段階で打刻します。まだ業務が残っているのに先に打刻をすると、残業時間が記録に反映されず、適切な給与支払いが行われない原因となります。
打刻後の残業は禁止するなど、時間外労働時間を適切に把握するためのルール整備を徹底しましょう。
出社しない場合の打刻方法
ここでは、オフィスに出社しない場合の打刻方法について解説します。
直行・直帰のケース
営業や外回りの業務で直行・直帰となる従業員がいる場合は、オフィスに立ち寄らなくても勤務時間を正しく記録できる仕組みを整えましょう。仕組みの例としては、仕事で用いるパソコンのログオンやログアウト時間を勤怠時間とみなす方法があります。
また、パソコンを持たないで外出する際には、メールやチャットを用いて勤怠を報告する方法も考えられます。
テレワークのケース
自宅などでテレワークを行う場合も、出勤・退勤の打刻は欠かせません。まず簡易的な方法として、メールや電話で報告を受けたり、ExcelやGoogleスプレッドシートに勤務時間を記入してもらったりすることで、勤務状況を把握できます。ただし、手作業での記録は入力漏れや誤記のリスクがあり、正確性や即時性に課題があります。
可能であれば、勤怠管理システムを用いてログイン・ログアウトの時間を自動で打刻する方法が望ましいです。システムを利用すれば、正確で公平な労働時間管理につながります。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
タイムカードを運用する際のポイント
ここでは、タイムカードを運用する際のポイントについて解説します。
打刻ミス・漏れなどの修正方法を明確にする
タイムカードを運用する際には、打刻ミス・漏れなどの修正方法を明確にしましょう。ミスが起きた際に、修正方法が不明確だと給与計算に影響が出る可能性があります。そこで、修正は必ず上長や管理者が確認して行うなど、ルールの明示が大切です。
現場が活用しやすいルールを設け、周知を徹底することで、信頼性の高い勤怠管理が実現できます。
本人だけが打刻できるようにする
タイムカードは本人が実際に勤務した記録を残すものです。代理打刻は不正につながる可能性があり、勤怠管理を行う際の障害になりかねません。そのため、本人以外の打刻禁止をルールとして徹底しましょう。
改ざんなど不正に対して罰則を設ける
タイムカードの運用に関するルールを定めて周知したとしても、従業員の意識が低いままでは効果が薄くなってしまいます。意識を高めるためには、不正に対して罰則を設ける取り組みが効果的です。懲戒処分や人事評価への反映など、不正を抑止できる効果的な項目を盛り込みましょう。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
タイムカードを運用する際の課題
ここでは、タイムカードを運用する際の課題について解説します。
ミスが起こりやすい
タイムカードは従業員自身が操作するため、打刻忘れや不正打刻など、人的ミスが発生しやすいという特徴があります。出勤時にうっかり打刻を忘れてしまうと、実際の勤務時間と記録にズレが出てくるため、後から修正が必要になるでしょう。
また、別の人がタイムカードを押す代理打刻も簡単であるため、不正が起きやすくなります。
作業に時間がかかる
タイムカードを紙で管理している場合は、勤怠データを集計して給与計算に反映させる作業に大きな手間がかかります。従業員数が多い場合は、月末や月初にタイムカードを回収し、1枚ずつ確認して計算する必要があるため、担当者に大きな負担がかかるでしょう。
さらに、打刻ミスがあった場合には、修正に時間を取られ、業務効率の低下につながります。
紛失する可能性がある
紙のタイムカードを使っている場合は、紛失するリスクもあります。従業員が持ち帰ったり、置き場所が不明になったりするなどのリスクが想定されるでしょう。もしカードを紛失してしまうと、その期間の出勤・退勤記録が残らず、労働時間を正しく把握できなくなります。
対策としては、タイムカードの持ち出しを禁止するなどのルール整備が考えられます。
リアルタイムで状況を把握できない
タイムカードは記録が紙や機械に残る形式であるため、リアルタイムで従業員の勤怠状況を把握しにくいです。担当者が内容を確認できるのはカードを回収・集計した後であるため、実際に誰が勤務中なのか、誰が休憩に入っているのかといった情報を随時把握するのは難しいでしょう。
リアルタイムで勤怠の状況を把握できれば、残業を多くしている従業員に対してアラートを出すことも可能です。
人によってルールが異なる
タイムカードの打刻ルールが明確に定められていない場合は、従業員によってルールの解釈が変わる可能性がある点も課題です。ある人は「出社時」に打刻し、別の人は「実際に業務を開始する直前」に打刻するなど、労働時間の算出に差が出てしまいます。
また、タイムカードを確認する担当者が、自身の判断で勤怠時間に手を加えてしまうことも考えられます。
効率化を図りたいなら勤怠管理システムの導入がおすすめ
タイムカードでは、打刻ミスや代理打刻、集計作業の負担、紙の紛失、リアルタイムでの状況把握の難しさなど、さまざまな課題が発生します。こうした問題を解決し、効率的で正確な勤怠管理を実現するには、勤怠管理システムの導入が有効です。
勤怠管理システムを利用すれば、従業員はスマートフォンやパソコンから簡単に打刻でき、データは自動で集計されます。これにより、人的ミスや集計作業の手間が大幅に削減され、勤怠記録の正確性が向上します。また、給与計算や人事システムと連携できるものも多く、法改正にもスムーズに対応可能です。
さらに、リアルタイムで勤務状況を把握できるため、長時間労働の早期検知や労務管理の改善も容易になります。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
まとめ
タイムカードは従来の勤怠管理で重要な役割を果たしてきましたが、打刻ミスや集計の手間、リアルタイム把握の難しさなどの課題があります。これらを解決し、正確で効率的な勤怠管理を実現するには、勤怠管理システムへの移行が有効です。
勤怠管理システムの導入をお考えでしたら、クラウド型勤怠管理システム「タッチオンタイム(Touch On Time)」がおすすめです。市場シェアNo.1※の実績を誇り、初期費用なし・月額300円/人から導入できます。30日間の無料トライアルと電話サポートも用意しているので、ITに不慣れな人でも安心して利用できるでしょう。
さまざまな労働環境でも打刻環境を整えられるよう、タイムレコーダーを自社開発しており、指紋とICカード打刻が可能な独立型端末「タッチオンタイムレコーダー」やお手持ちの端末で利用できる顔認証打刻「Facee(フェイシ―)」で、労働条件に影響されることなく打刻が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
※2023年 富士キメラ総研調べ 勤怠管理SaaS市場 利用ID数
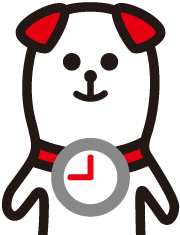
- この記事の執筆者
- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
- 受賞歴:「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」勤怠管理システム部門
ITトレンド Good Productバッジ 2022