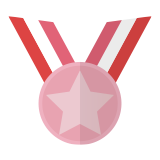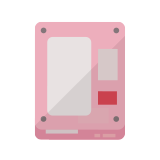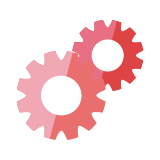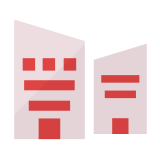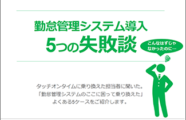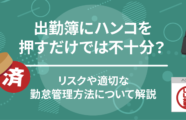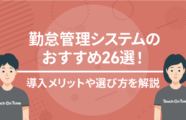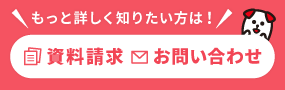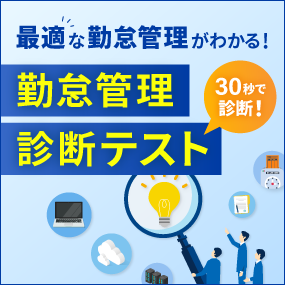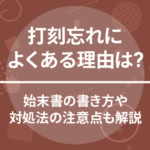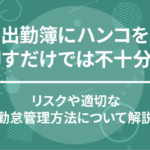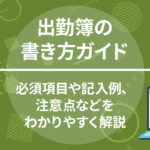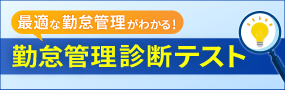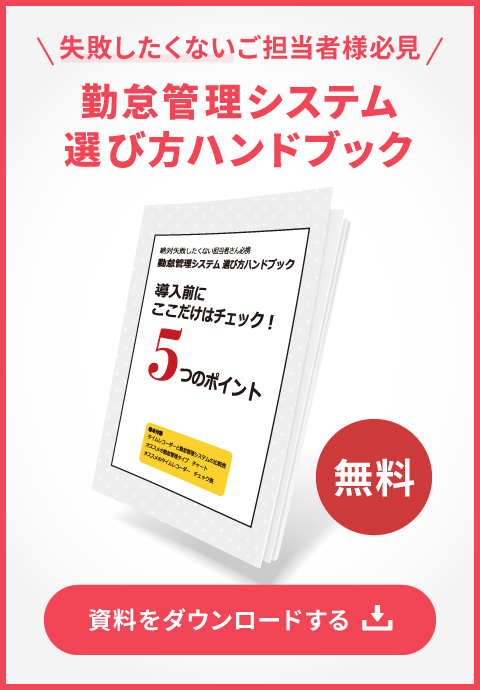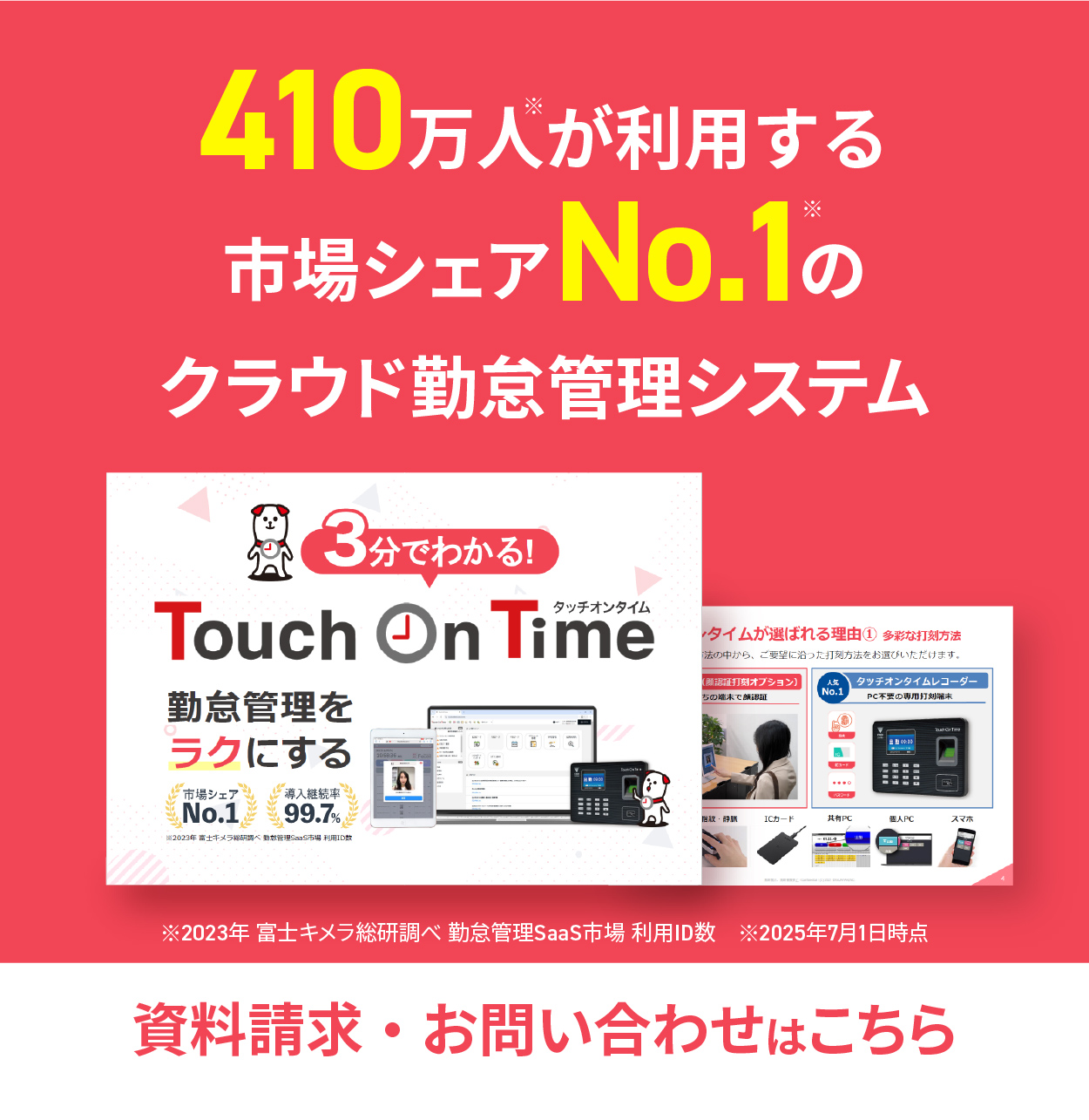出勤簿の保存期間は何年?注意点や電子化のメリット・デメリットまで解説
勤怠管理システム
働き方改革
打刻
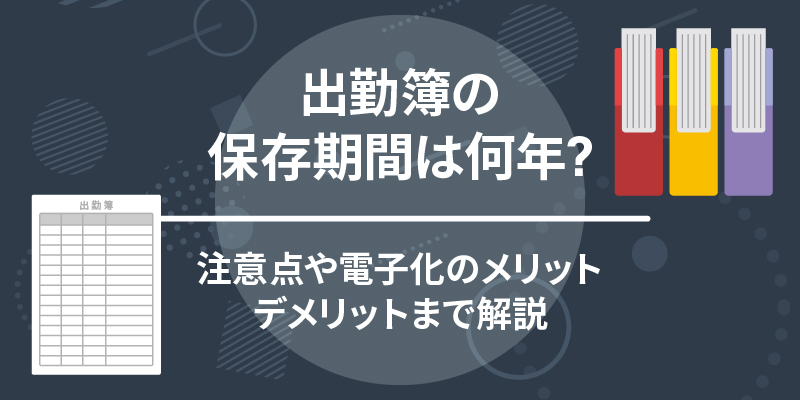
公開日:2025年10月17日
こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。
出勤簿の保存期間は、法改正で原則5年となりましたが、当面3年の経過措置もあり複雑です。この記事では、法律で定められた保存期間とその重要性を詳しく解説します。
また、紙での保管や勤怠管理システムによる電子化のメリット・デメリットも比較し、法令を順守しながら業務を効率化するためのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- 出勤簿の目的と法的な位置づけ、タイムカードとの違い
- 法改正で変わった出勤簿の保存期間と注意点
- 紙・Excel・システムによる保管方法の特徴
- 電子化による業務効率化のメリットとデメリット
出勤簿とは
出勤簿は、労働時間を正確に把握するための法定帳簿です。ここではその目的や対象者、タイムカードなどとの違いを詳しく解説します。
参考:労働基準法 第百109条 | e-Gov 法令検索
出勤簿の目的
出勤簿の目的は、従業員の労働時間を客観的に把握し、適正な給与支払いの基礎とすることです。加えて、時間外労働の上限規制を守り、従業員の健康を守るためにも活用されます。
万一の労使トラブルの際には企業の対応を示す証拠となり、適正な労務管理とコンプライアンスの徹底に欠かせません。
※参考:労働基準法 第109条 | e-Gov 法令検索
※参考:労働基準法 第32条・34条 | e-Gov 法令検索
※参考:労働基準法 第35条・36条 | e-Gov 法令検索
出勤簿の対象者
出勤簿の記録対象は、雇用形態を問わず、原則として全ての従業員です。労働時間管理の対象外と思われがちな管理監督者や裁量労働制の適用者も、適切に労働時間を把握するため記録が求められます。なお、派遣社員については、管理責任を負う派遣先企業が作成・管理の義務を負います。
出勤簿とタイムカードの違い
タイムカードは、出退勤の時刻を客観的に記録したデータそのものを指します。一方で出勤簿は、タイムカードの記録を基に休憩や時間外労働などを反映して正確な労働時間を算出し、会社が承認した帳簿です。給与計算の根拠となるのは元データではなく、確定した出勤簿という点に違いがあります。
出勤簿と労働者名簿の違い
出勤簿は、始業・終業時刻といった「日々の労働時間」を記録する帳簿です。一方、労働者名簿は氏名や履歴など「労働者個人の情報」を管理するもので、記録の目的と内容が異なります。
どちらも法定三帳簿に含まれ、労働基準監督署の調査で提出が求められるため、それぞれの役割を理解し適切な管理が求められます。
※参考:労働基準法 第107条・108条・109条 | e-Gov 法令検索
出勤簿と賃金台帳の違い
出勤簿と賃金台帳は管理する情報が異なります。出勤簿が日々の労働時間を記録するのに対し、賃金台帳はその時間に基づいて算出された給与額や手当などを記載するものです。
両者は連携しており、正確な賃金台帳を作成するためには、その基となる出勤簿の勤怠記録が正しくなければなりません。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
出勤簿の保存期間
出勤簿の保存期間は法律で定められていますが、原則と例外があり一律ではありません。それぞれのケースについて解説します。
出勤簿の保存期間は法改正で「5年」が原則
2020年の労働基準法改正により、出勤簿の保存期間は従来の3年から原則5年へと延長されました。起算日から5年間は適切に保管する義務があり、期間内に破棄した場合は法律違反として30万円以下の罰金が科される恐れがあります。期間の順守と合わせて、適切に保存しましょう。
※参考:労働基準法 第109条| e-Gov 法令検索
※参考:労働基準法 第120条 |e-Gov 法令検索
経過措置につき当面は「3年」でも可
労働基準法改正に伴う経過措置として、出勤簿の保存期間は当面の間「3年」とすることが認められています。ただし、これは将来の「5年」保存義務化へ向けた暫定的な扱いです。
措置の終了に備え、今のうちから5年保存が可能な体制を整えておくとスムーズに対応できます。最新情報は厚生労働省の公式サイトなどで確認しましょう。
保存期間が「7年」になる場合もある
賃金台帳を源泉徴収簿と兼用している場合、国税通則法に基づき7年間の保存が必要です。これは、源泉徴収簿自体に7年の保管義務があるためです。労働基準法の経過措置(当面3年)とは関係なく7年の保存が求められるため、両者を一体で管理している企業は注意しましょう。
※参考:No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|国税庁
※参考:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁
※参考:国税通則法 第70条|e-Gov 法令検索
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
出勤簿の保存はなぜ重要か
出勤簿の保存は、法律で定められた義務であると同時に、労働基準監督署の調査や従業員とのトラブルに備える上で重要です。以下で、理由を詳しく解説します。
労働基準法で保存が義務付けられているため
労働基準法により、企業は従業員の出勤簿やタイムカードといった勤怠記録を保存する法的義務を負っています。保存期間は原則5年(当面は3年)と定められており、この義務を怠った場合には、30万円以下の罰金が科される恐れがあります。法令を順守するためにも、適切な期間、確実な保存が必要です。
※参考:労働基準法 第109条|e-Gov 法令検索
※参考:労働基準法 第120条|e-Gov 法令検索
労働基準監督署の調査で必要になるため
労働基準監督署による調査(臨検監督)では、適正な勤怠管理が行われているかが厳しく確認されます。その際、出勤簿は従業員の労働時間を客観的に証明する証拠として、提出が必須です。適切に保存しておらず提示できない場合、法令違反を指摘され、是正勧告や罰則の対象となるリスクがあります。
従業員とのトラブルを防ぐため
従業員から未払い残業代などを請求された場合に、出勤簿は企業が正当性を主張するための証拠となります。出勤簿の保管がなければ正確な勤務実態を証明できず、トラブルが深刻化する恐れもあるでしょう。賃金請求の時効は3年(原則5年)と長いため、安易な破棄は禁物です。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
出勤簿の保管方法
出勤簿の保管方法は、大きく分けて3つあります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、自社に最適な方法を選びましょう。
紙媒体で保管する
紙の出勤簿は、ファイルにとじて施錠できるキャビネットで管理するのが一般的な方法です。手軽に始められる一方、手作業での集計には転記ミスや計算間違いが起こりやすい点が課題になります。また、書類の紛失や改ざんのリスク、従業員数に応じた保管スペースの確保も考慮が必要です。
Excelで管理する
Excelは、自社の運用に合わせてフォーマットを自由に設計できる柔軟性が強みです。関数を駆使すれば労働時間の集計が自動化され、業務効率化につながるでしょう。
一方で、手入力によるミスや誤削除が起こりやすいため、マニュアルを整備するなど慎重な取り扱いが求められます。
勤怠管理システムで電子保存する
出勤簿の作成や集計には手間や管理負担がかかりますが、勤怠管理システムを使えば、打刻データから自動で出勤簿を作成でき、集計作業の手間を大幅に削減できます。データは電子保存されるため、紛失や保管場所の心配もなく、従業員の増減にも柔軟に対応可能です。
このように、正確で効率的な勤怠管理を実現したい企業には、システムの導入がおすすめです。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
出勤簿の注意点
出勤簿は労働時間を証明する重要な書類です。後々のトラブルを防ぐためにも、以下のポイントを正しく理解し、適切に運用しましょう。
押印のみは認められない
出勤日に印鑑を押すだけの方法は、労働時間を客観的に記録したとは見なされません。出勤簿は賃金台帳の作成根拠であり、労働基準法に基づき労働日数や時間数などを正確に記録する義務があります。
押印のみではこれらの法的要件を満たせないため、始業・終業時刻を分単位で記録できる形式へ変更しましょう。
※参考:労働基準法 108条 | e-Gov 法令検索
※参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
労働時間は切り捨てずに記録すること
労働時間は、原則として1分単位で記録しなければなりません。15分未満の時間を切り捨てる運用は、働いた分の賃金が支払われないため違法となる恐れがあります。
ただし例外として、1か月の時間外労働の合計時間については、就業規則に明記されていれば、30分未満を切り捨てるなどの事務的な端数処理が認められています。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
出勤簿を勤怠管理システムで電子化するメリット
勤怠管理をシステム化すると、業務効率化や人的ミスの防止につながります。以下で、おもなメリットを解説します。
業務効率化につながる
勤怠管理システムは、手作業だった業務を自動化するため、業務効率化につながります。タイムカードの集計や給与計算ソフトへのデータ転記が不要になり、担当者の負担が軽減されることもメリットです。
従業員も自身の勤務状況をいつでも確認できるため、勤怠に関する問い合わせ対応が減り、管理者はコア業務に集中できます。
入力ミスや計算ミスを防げる
勤怠管理システムの導入によって、データの正確性が大幅に向上します。手作業での計算や入力ミスを防げるため、正確な勤怠データの管理が可能です。リアルタイムで自動記録される打刻データにより、給与計算は正確になり、コンプライアンス強化にもつながります。
自社の既存システムと連携できる
勤怠管理システムは、給与計算ソフトや人事・会計システムなど、既存の社内システムと連携可能です。これまで手作業だった勤怠データの転記が不要となり、二重入力の手間や入力ミスを解消します。
また、法的に長期間の保存が義務付けられている勤怠データをシステム上で一元管理できるため、紙での保管のように場所やコストがかかりません。API連携などを通じてデータは自動で同期され、過去の履歴も探しやすくなるため、勤怠から給与計算までをスムーズに管理でき、バックオフィス業務全体の効率化につながるでしょう。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
出勤簿を勤怠管理システムで電子化するデメリット
便利な勤怠管理システムですが、導入を検討する際には以下のようなデメリットも考慮する必要があります。
システムトラブルが起こる可能性もある
システム運用には、サーバーダウンや通信障害といったトラブルのリスクが伴います。特にクラウド型はネット環境に依存するため、障害発生時には打刻やデータ閲覧ができなくなる可能性があります。
重要な勤怠データが消失する危険性もゼロではないため、システムのバックアップ体制や障害時のサポート内容を確認しておきましょう。
システムは通信環境により一時的に利用しにくくなる可能性も考慮しておきましょう。勤怠データを守るため、検討中のシステムのセキュリティ基準が自社の水準を満たすか、日々のバックアップ体制や万が一のサポート内容はどうか、といった点を事前に確認しておくことをおすすめします。
システム導入時にコストがかかる
システムの導入には、初期費用や月額利用料といった直接的なコストに加え、データ移行や従業員への操作説明といった間接的なコストも発生します。本格稼働までに数か月を要することも珍しくなく、これらの費用や工数は導入時の負担となるため、将来の業務効率化と見合うか慎重な検討が求められます。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
まとめ
出勤簿は法令で保存期間が定められており、正確な管理が求められます。しかし、紙やExcelでの管理には計算ミスや保管の手間といった限界があります。こうした課題を解消する方法として、勤怠管理システムの導入は有効です。
勤怠管理システムの導入を検討しているなら、クラウド型勤怠管理システム「タッチオンタイム(Touch On Time)」がおすすめです。市場シェアNo.1※の実績を誇り、初期費用は無料、月額は1人あたり300円から導入できます。30日間の無料トライアルと電話サポートも用意しているので、ITに不慣れな人でも安心して利用できるでしょう。
さまざまな労働環境でも打刻環境を整えられるよう、タイムレコーダーを自社開発しており、指紋とICカード打刻が可能な独立型端末「タッチオンタイムレコーダー」やお手持ちの端末で利用できる顔認証打刻「Facee(フェイシ―)」で、労働条件に影響されることなく打刻が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
※2023年 富士キメラ総研調べ 勤怠管理SaaS市場 利用ID数
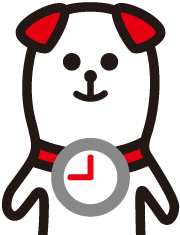
- この記事の執筆者
- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
- 受賞歴:「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」勤怠管理システム部門
ITトレンド Good Productバッジ 2022