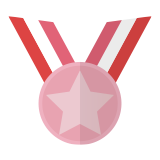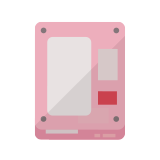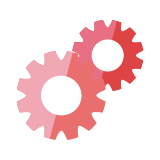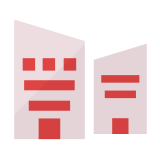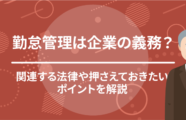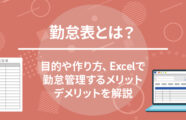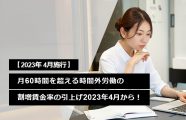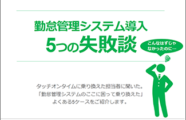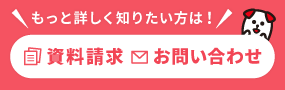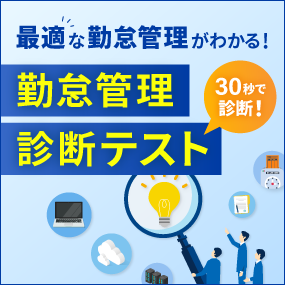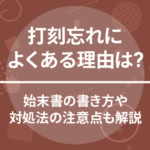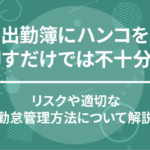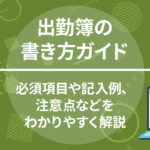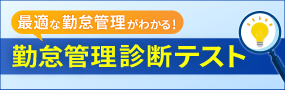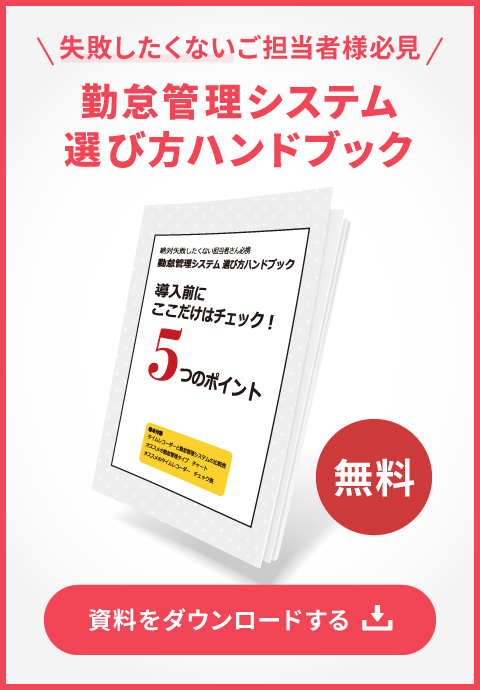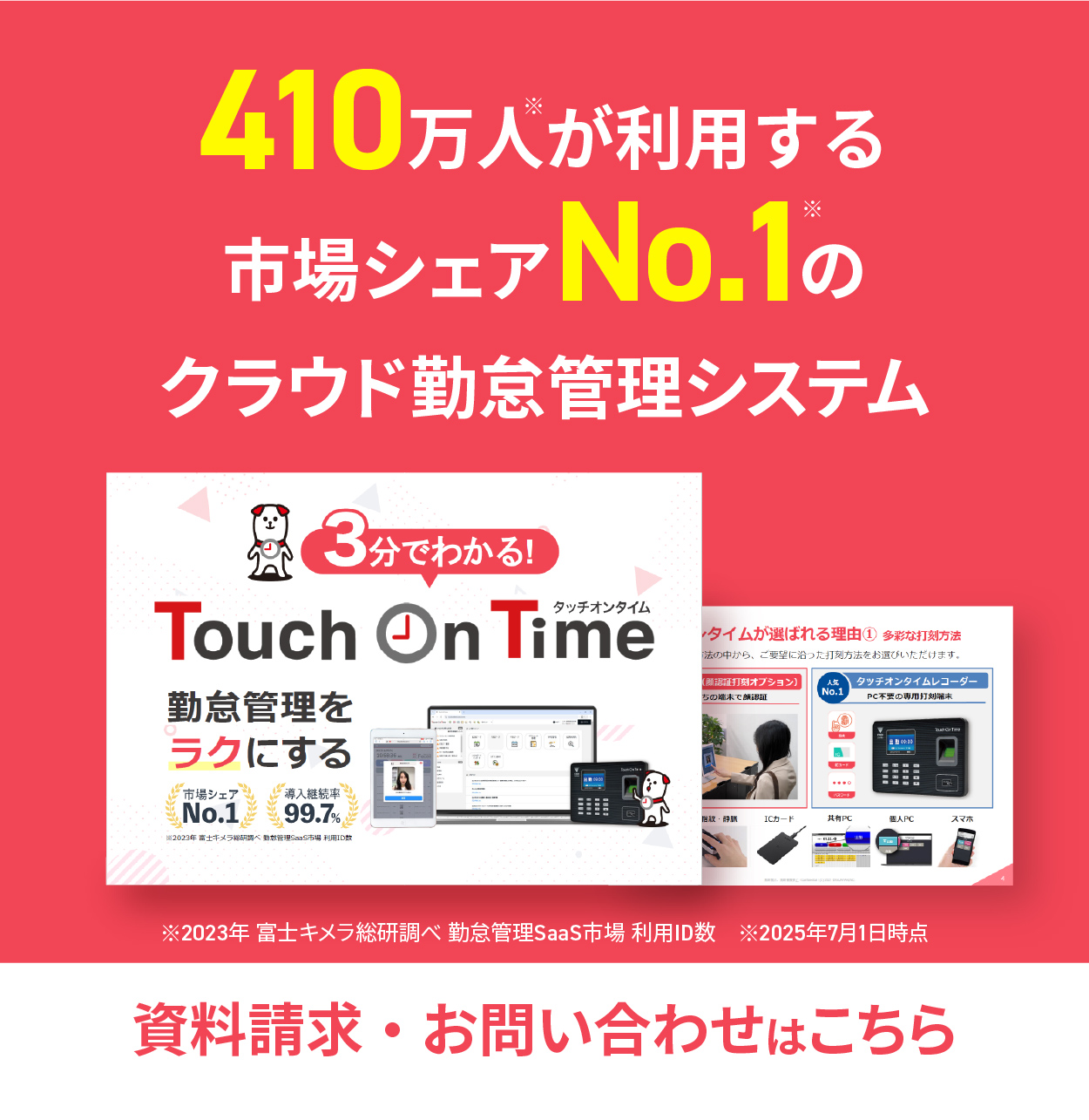出勤簿の書き方ガイド|必須項目や記入例、注意点などをわかりやすく解説
勤怠管理システム
働き方改革
打刻
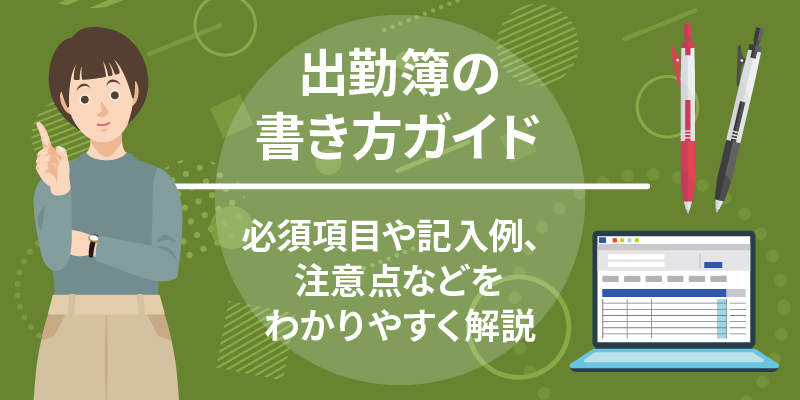
公開日:2025年10月17日
こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。
出勤簿は、企業に作成が義務付けられた帳簿のひとつです。記載項目にも決まりがありますが、正しい書き方が分からず困っている人も多いでしょう。
本記事では、出勤簿の書き方を項目別に詳しく解説します。出勤簿の記入例や作成方法、作成時の注意点なども解説するので、ぜひ参考にしてください。
- 出勤簿の目的とタイムカードとの違い
- 出勤簿の必須記載項目と正しい書き方
- 保存期間や作成時の注意点と法令遵守のポイント
- 出勤簿作成を効率化する勤怠管理システムの活用
出勤簿とは?
出勤簿とは、従業員1人ひとりの出勤日や労働時間などを記録する帳簿です。賃金台帳や労働者名簿と同じ法定三帳簿のひとつであり、法律により作成・保管義務が定められています。
また、2019年の働き方改革関連法改正により、出勤簿は管理監督者を含む全ての労働者について作成することとなりました(高度プロフェッショナル制度対象労働者は除く)。
※参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
※参考:労働基準法第109条|e-Gov法令検索
出勤簿を作成する目的
出勤簿を作成する目的は、従業員の勤怠を正確に管理することです。労働関連の法律では、労働日数や労働時間、休憩時間にさまざまな制限が設けられており、これを守るためには日々の記録が欠かせません。
出勤簿は、こうした法令に沿った適切な労務管理を実現するための基本資料であり、同時に法令順守の証拠としても重要な役割を果たします。そのため、正しい方法で作成・管理することが求められます。
出勤簿とタイムカードの違い
タイムカードは主に始業時刻と終業時刻を記録するツールですが、出勤簿はこれに加えて労働時間や時間外労働など、勤怠情報を網羅的にまとめた帳簿です。
多くの企業では、タイムカードの打刻情報をもとに出勤簿を作成します。つまり、タイムカードが日々の勤怠を記録する手段であるのに対し、出勤簿はそれらのデータを整理・集計して管理するための重要な資料といえます。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
出勤簿の記載項目と書き方
出勤簿には必須の記載項目があるため、情報に抜け漏れがないよう注意が必要です。それぞれの項目ごとに、記載内容や書き方を解説します。
従業員の氏名
出勤簿は従業員ごとに作成する必要があるため、誰の出勤簿なのかが明確に分かるよう、従業員の氏名を必ず記載します。必要に応じて、従業員の所属部署や役職などを記載してもよいでしょう。
出勤日・出勤日数
従業員が出勤した日付と、出勤日数の合計を記載します。遅刻や早退、休日出勤や有給休暇などが明確に分かるよう記載することが大切です。また、遅刻や早退があった日は、備考欄などに理由を記載するとよいでしょう。
なお、名目上は「出勤」ですが、在宅勤務のようにオフィスに出勤しない日も出勤日としてカウントする必要があります。
労働時間・始業時刻・終業時刻・休憩時間
出勤日ごとの労働時間や、始業時刻・終業時刻、休憩時間などを記載します。残業時間も含め、従業員が実際に労働した「実労働時間」を記録しましょう。
実労働時間は始業時刻と終業時刻の差分から、休憩時間を差し引くことで計算可能です。例えば、始業時刻が10時、終業時刻が20時で休憩時間が1時間だった場合、実労働時間は9時間となります。
時間外労働の日付・時刻・時間数
時間外労働とは、法定労働時間の「1日8時間・週40時間」を超える労働のことです。例えば、従業員の1日の実労働時間が9時間だった場合、そのうち1時間は時間外労働となります。
時間外労働には割増賃金を支給するため、通常の労働とは分けて記載する必要があります。時間外労働のあった日付と開始時刻・終業時刻、時間数を記載しましょう。
※参考:労働基準法第32条|e-Gov法令検索
※参考: 労働基準法第37条|e-Gov法令検索
休日労働の日付・時刻・時間数
従業員が休日労働をした日付や始業時刻・終業時刻、合計の時間数についても記載します。
労働基準法第35条の規定により、企業は従業員に「週1日もしくは4週を通じて4日」の休日を与えなければならないと定められており、この休日を法定休日といいます。法定休日と法定外休日では割増賃金の扱いが異なるため、それぞれ分けて記載することが大切です。
※参考:労働基準法第35条|e-Gov法令検索
※参考:労働基準法第37条|e-Gov法令検索
深夜労働の日付・時刻・時間数
深夜労働とは、22時から翌5時までの労働のことです。例えば、従業員が20時から23時まで残業をした場合、22時から23時までの1時間は深夜労働として扱われます。
時間外労働や休日労働と同様、深夜労働には割増賃金を支払う必要があります。従業員が深夜労働をした場合は、その日付や開始時刻・終業時刻、合計の時間数を記載しましょう。
出勤簿の記入例
出勤簿のフォーマットは定められていませんが、全ての記載項目を網羅する必要があります。インターネットで検索すると、サンプルやフォーマットが数多く見つかるため、必要に応じて参考にするとよいでしょう。
以下に、厚生労働省の資料を参考とした出勤簿の記入例を紹介します。

勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
出勤簿の保存期間
労働基準法第109条により、出勤簿の保存期間は原則5年と定められています。月末や賃金計算期間の末日など、出勤簿に最後に記入した日を起算日とします。
なお、経過措置として、当面の間は保存期間を3年とすることが可能です。
※参考:労働基準法第109条|e-Gov法令検索
※関連記事:出勤簿の保存期間は何年?注意点や電子化のメリット・デメリットまで解説
出勤簿の保存義務に違反した場合の罰則
労働基準監督署の調査により保存義務違反が発覚した場合は、是正勧告や改善指導の対象になります。企業側が是正勧告や指導に従わず、悪質性が認められる場合は、企業名を公表されたり、罰則を科されたりする恐れもあります。
労働基準法第120条の規定に基づき、出勤簿の保存義務に違反した場合の罰則は30万円以下の罰金です。罰金刑を回避できても、法令違反が明るみに出れば社会的信用の低下は免れないでしょう。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
出勤簿を作成する際の注意点
出勤簿を作成する際は、以下の3つのポイントに注意が必要です。
労働時間は1分単位で正確に記録する
労働基準法第24条により、企業は賃金を全額支払わなければならないと定められています。この規定を順守するためには、労働時間を10分や15分などの単位で丸めず、1分単位で正確に管理しなければなりません。
なお、1日単位の労働時間の端数の切り上げなど、一部例外的に端数処理が認められるケースもあります。
※参考:労働基準法第24条|e-Gov法令検索
※参考:労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう|厚生労働省
印鑑だけの出勤簿は認められない
従来は、出勤日のところに押印するだけの出勤簿を採用している企業も少なくありませんでした。しかし、印鑑だけの出勤簿では従業員の労働時間や休憩時間などを把握できず、出勤簿の記載内容としては不十分です。
印鑑だけの出勤簿を運用している場合は、必要な情報を記録できるフォーマットへ変更しましょう。
最新の法令・ガイドラインを確認する
労働に関する法令やガイドラインは、継続的に見直されています。出勤簿の書き方や管理方法などについても、今後ルールは変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが大切です。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
出勤簿の作成方法
出勤簿を作成する方法としては、以下の3つのパターンが考えられます。
手書きで記入する
紙の出勤簿に始業時刻・終業時刻や休憩時間などの欄を設け、従業員に手書きで記入してもらう方法です。紙とペンさえあれば手軽に導入でき、コストを抑えやすいというメリットがあります。従業員数の少ない、比較的小規模な事業所に適した方法です。
手書きの運用には注意が必要
原則として、従業員の労働時間は使用者による現認や、タイムカードやパソコンの使用時間記録などの客観的な方法により把握しなければなりません。例えば、従業員が目視で始業時刻・終業時刻を確認し、出勤簿に書き込むという運用方法では、労働時間の管理が不十分と判断される恐れがあります。
やむを得ない場合は自己申告制も認められていますが、厚生労働省のガイドラインに定められた措置を講じる必要があります。詳しくは下記のガイドラインを確認してください。
※参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
Excelのテンプレートを活用する
Excelを使って出勤簿を管理する方法です。便利なテンプレートが公開されているケースも多いため、出勤簿を手軽に作成できます。関数やマクロを活用すれば、労働時間や休憩時間などを自動で集計することも可能です。すでにExcelを導入済みの企業なら、新たなコストも発生しません。
ただし、法改正があった場合は、フォーマットや関数を変更しなければならない可能性もあります。
勤怠管理システムを導入する
勤怠管理に特化したソフトウェアやクラウドサービスを利用する方法です。従業員の勤怠データをリアルタイムで集計でき、出勤簿管理の効率化を図れます。
日々の労働時間や休憩時間はもちろん、時間外労働時間や休日労働時間なども自動的に集計可能です。また、システムの自動アップデートにより、最新の法改正に即した運用を実現できます。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
出勤簿管理に勤怠管理システムを活用するメリット
最後に、出勤簿管理に勤怠管理システムを活用するメリットについて解説します。
業務効率化につながる
勤怠管理システムを導入すると、勤怠データの収集・集計作業を自動化でき、業務効率が向上します。給与計算システムや人事システムなど、外部システムとの連携が可能な製品も多いため、人事労務業務全体の効率化にもつながるでしょう。
人的ミスを減らせる
手作業での入力や転記作業が不要となることで、記入漏れや計算ミスなどのヒューマンエラーを削減できます。これにより、正確な労務管理や給与計算を実現しやすくなり、法令違反のリスクを低減することが可能です。
保管コストを削減できる
出勤簿には原則5年間の保存義務があります。紙の出勤簿はかさばりやすいため、全従業員分の保管スペースを確保することは容易ではありません。
勤怠管理システムなら、打刻時間や労働時間などの情報をデータとして管理できます。紙の出勤簿やタイムカードなどと異なり、物理的な保管場所が不要なため保管コストの削減が可能です。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
まとめ
出勤簿には、出勤日や労働時間、時間外労働時間や休日労働時間などさまざまな項目を記載します。法令順守を徹底していることを証明するために不可欠な帳簿ですので、最新の法律やガイドラインに基づき適切に作成・管理しましょう。
出勤簿を効率的に作成・管理するなら、勤怠管理システムがおすすめです。クラウド型勤怠管理システム「タッチオンタイム(Touch On Time)」は市場シェアNo.1※の実績を誇り、初期費用は無料、月額は1人あたり300円から導入できます。30日間の無料トライアルと電話サポートも用意しているので、ITに不慣れな人でも安心して利用できるでしょう。
さまざまな労働環境でも打刻環境を整えられるよう、タイムレコーダーを自社開発しており、指紋とICカード打刻が可能な独立型端末「タッチオンタイムレコーダー」やお手持ちの端末で利用できる顔認証打刻「Facee(フェイシ―)」で、労働条件に影響されることなく打刻が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
※2023年 富士キメラ総研調べ 勤怠管理SaaS市場 利用ID数
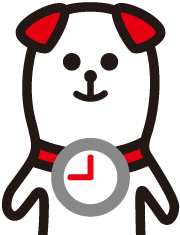
- この記事の執筆者
- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
- 受賞歴:「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」勤怠管理システム部門
ITトレンド Good Productバッジ 2022