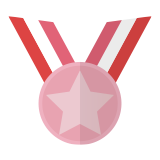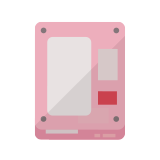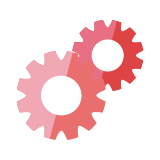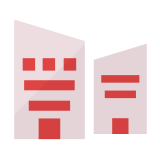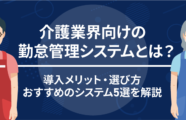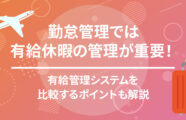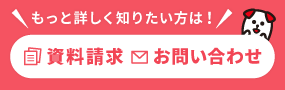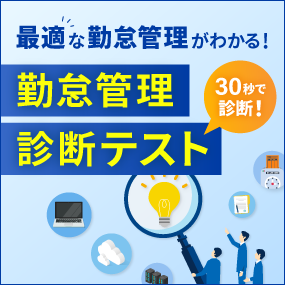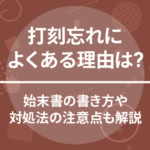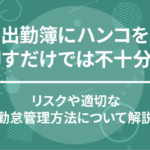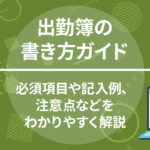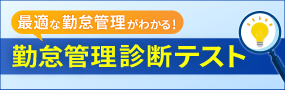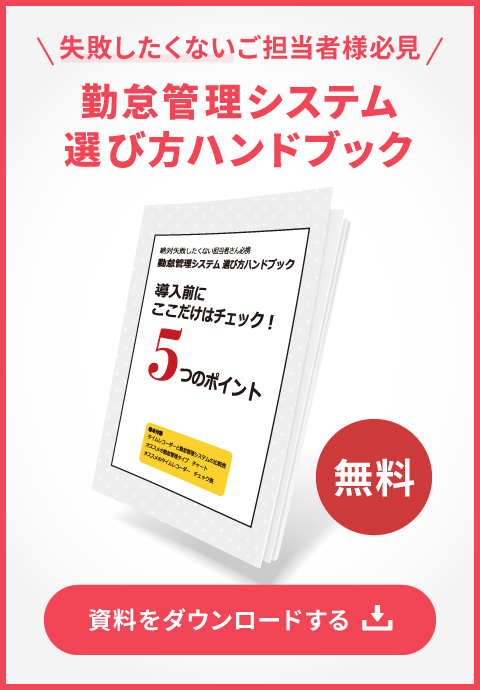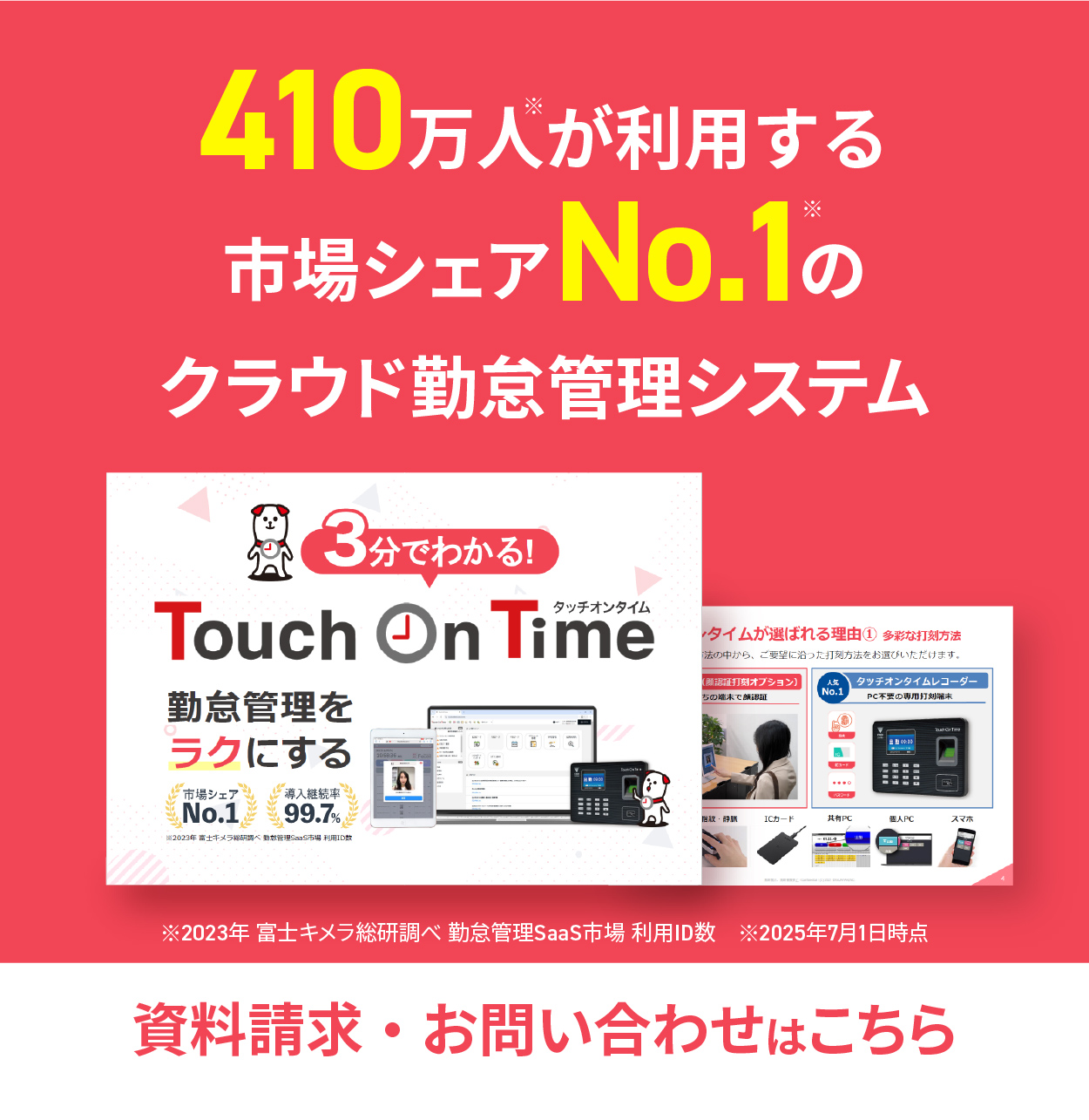勤怠管理におけるルールとは?知っておきたい法律や社内ルールについて解説
勤怠管理システム
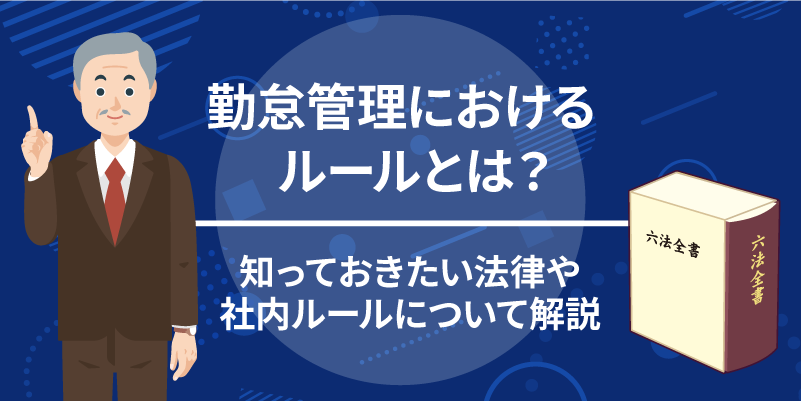
公開日:2025年8月19日
こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。
従業員の勤怠データは、法律に基づき正確に管理する必要があります。ずさんな勤怠管理は労務トラブルの原因となり、企業イメージが低下するだけでなく、罰則の対象にもなりかねません。本記事では、勤怠管理の担当者が知っておきたい法律や、社内ルールの設定について詳しく解説します。
- 勤怠管理に関わる法令について
- 労働基準法に基づく時間外労働・割増賃金・休日管理などの基本ルール
- タイムカードやシステムなど代表的な勤怠管理手法とその特徴
- 社内ルールの設定と違反時の対応について
勤怠管理にルールが求められる理由
まずは、勤怠管理に厳格なルールが求められる理由から紹介します。
法律で定められた義務を果たすため
従業員の勤怠管理は、法律で定められた企業の義務です。企業は各種法律のルールに基づき、従業員の労働時間や休憩時間などを正確に管理しなければなりません。また、国が推進する「働き方改革」を実現するためにも、企業には勤怠管理を適正に行い、従業員の過重労働を防止する義務があります。
正確な給与計算を実現するため
企業は従業員に対して、それぞれの労働に応じた給与を支払わなければなりません。
そして、給与を正確に計算するためには、労働時間の把握が不可欠です。労働時間の集計結果に誤りがあると、給与の金額にも誤差が生じてしまいます。給与計算のミスは各種保険料や税金の計算にも影響を及ぼすため、企業には法律に則った厳格な勤怠管理が求められます。
企業経営の健全化を図るため
勤怠管理が疎かな企業は「従業員を大切にしていない」という印象を持たれてしまい、人材獲得にも悪影響を及ぼしかねません。一度下がった企業イメージを向上させることは難しく、企業の経営そのものにも打撃を受ける恐れがあります。
勤怠管理の正確性と透明性を担保することは、経営の健全化につながり、企業の利益にも影響をもたらすでしょう。
トラブルに備えるため
労働時間を正確に管理することは、トラブルの回避にも役立ちます。例えば、給与計算を正確に行えば、給与不支給による従業員とのトラブルを回避できます。
また、1人ひとりの労働時間を把握できていれば、残業が多い部署や従業員に対して適切なアプローチをとることが可能です。過重労働による健康被害を未然に防ぎ、訴訟リスクも低減できるでしょう。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
勤怠管理における労働基準法のルール・注意点
労働基準法には、勤怠管理に関連するさまざまな規定があります。ここからは、勤怠管理における労働基準法のルールや、企業が注意すべきポイントをおさらいしましょう。
労働時間の上限
労働基準法第32条により、従業員の労働時間は「1日8時間・週40時間」までと定められており、これを「法定労働時間」といいます。
また、企業が従業員に法定労働時間を超えて労働させるには、労働基準法第36条を根拠とする「時間外・休日労働に関する協定(以下、36協定)」を締結しなければなりません。
※参考:労働基準法|e-Gov 法令検索
労働時間の客観的把握の義務
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間の客観的把握が義務付けられています。そのため、企業はタイムカードやICカード、パソコンの使用時間などの記録から、従業員の労働時間を客観的に把握しなければなりません。なお、従業員の自己申告に基づく勤怠管理は原則推奨されていないため注意が必要です。
※参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
時間外労働の上限
法定労働時間を超える時間外労働には、上限規制が設けられています。36協定を締結済みであっても、時間外労働は原則「月45時間・年360時間」の範囲内に収めなければなりません。
なお、特別条項付きの36協定を結べば、上記の制限を超えた時間外労働が可能です。ただし、その場合も、時間外労働には以下のような上限があります。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が2〜6か月平均で全て月80時間以内
- 月45時間を超える労働は年6か月まで
休憩時間の付与
労働基準法第34条により、従業員の労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません。また、休憩時間の付与には、以下の3つの原則があります。
- 途中付与の原則:休憩は労働の途中に付与する
- 一斉付与の原則:休憩は全ての従業員に一斉に付与する※例外有
- 自由利用の原則:休憩中は労働から完全に解放し、自由に過ごせるようにする
※参考:労働基準法|e-Gov 法令検索
休日の付与
労働基準法第35条により、企業は従業員に少なくとも「週1日または4週を通じて4日」の休日を与える必要があります。ただし、労働時間の上限(1日8時間・週40時間)を加味すると、従業員を1年間に働かせられる日数は260日程度です。そのため、年間に付与すべき休日は365日-260日=105日です。
※参考:労働基準法|e-Gov 法令検索
有給休暇の付与と取得義務
雇用から6か月以上継続して勤務しており、そのうち全労働日の8割以上出勤している従業員には、年10日以上の有給休暇を付与する必要があります。また、年10日以上の有給休暇を付与する従業員については、少なくとも年5日の有給休暇を取得させなければなりません。
※参考:労働基準法|e-Gov 法令検索
年5日の年次有給休暇の確実な取得|東京労働局
割増賃金の支給
法定労働時間を超える時間外労働に対しては、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。なお、時間外労働が月60時間を超えた分については、50%以上の割増賃金が必要です。また、法定休日の労働には35%以上、深夜労働(22時から翌5時まで)には25%以上の割増賃金を支給します。
※参考:労働基準法|e-Gov 法令検索
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
代表的な勤怠管理の方法
これまでに紹介した法的ルールを踏まえ、代表的な勤怠管理の方法とそれぞれの特徴について解説します。
人事・労務担当者が出勤簿で管理する
人事・労務担当者が、紙やExcelの出勤簿で勤怠を管理する方法です。導入コストが低い点がメリットですが、集計作業の手間が大きく、記入ミスや改ざんのリスクもあります。Excel管理であれば、関数の活用によりある程度の効率化が可能です。
なお、この方法は従業員の自己申告制となるため、厚生労働省のガイドラインでは原則推奨されていません。
タイムカードで管理する
従業員がタイムレコーダーにタイムカードを挿入し、出退勤時刻を打刻する方法です。客観的な記録が残るため、紙やExcelで管理するよりもデータの正確性を向上させられます。ただし、タイムカードの回収・集計には手間がかかるうえ、不正打刻が起こりやすい点が課題です。また、直行直帰やテレワークなど多様な勤務形態の記録には対応しにくく、運用が制限される場合があります。
勤怠管理システムで管理する
勤怠管理機能のあるシステムを導入する方法です。パソコンからだけでなく、スマートフォンやタブレットなどから打刻ができる場合が多く、勤怠情報をリアルタイムで管理できます。インターネット環境があればどこからでもアクセスできるため、テレワークをはじめとした多様な勤務形態にも対応しやすいのが特徴です。
また、集計作業を自動化できるため担当者の負担が軽減され、人的ミスを防ぎやすいというメリットもあります。給与計算システムや人事システムとの連携が可能な製品も多く、データの一元管理や自動反映が可能です。
さらに、法改正時にもシステムのアップデートにより速やかに対応できるため、法令遵守にも役立ちます。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
勤怠管理には社内ルールの設定も必要
正確な勤怠データを収集するためには、社内ルールの設定が不可欠です。以下の3つについて、自社に合わせたルールを作成しましょう。
出勤・退勤の打刻に関するルール
労働時間を正確に把握するためには、打刻に関する明確なルールが必要です。打刻は出退勤の直後に行うのが一般的ですが、タイミングがあいまいになるケースも少なくありません。例えば、出勤後に制服への着替えや朝会などがあるケースです。基本的には、着替えや朝会に強制力がある場合は、その時間も労働時間としてカウントする必要があります。
残業や有給休暇に関するルール
時間外労働(残業)の上限規制を遵守するには、従業員の理解と協力が不可欠です。労働時間の上限を明確に周知し、規定を超える残業は原則として承認しないなどの仕組みを整えましょう。残業を行う場合は、必ず上司の事前承認を得るルールを徹底することが重要です。
また、有給休暇については事前申請制を導入することで、業務の調整がしやすくなり、他の従業員への負担を軽減できます。
雇用形態や勤務形態に合わせたルール
正規雇用だけでなく、派遣やパートなど複数の雇用形態の従業員がいる場合は、それぞれに合わせた勤怠管理のルールづくりが必要です。
また、シフト制やフレックスタイム制などの勤務形態を採用している場合も、働き方に応じたルール設定が欠かせません。例えば、フレックスタイム制ではコアタイムや休憩時間などについて、事前に決まりを作っておくことが大切です。
なお、雇用形態や勤務形態ごとのルールを作成する際は、それぞれに関連する法律を忘れずに確認しましょう。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
ルールを守らない従業員への対策も重要
法令遵守を徹底するためには、従業員一人ひとりが勤怠管理ルールを遵守することが前提です。企業は現場での運用状況を定期的に把握し、ルール違反があれば速やかに指導・是正を行う体制を整える必要があります。
また、ルール違反が従業員の自主的なものとは限らず、上司からの不正な圧力や強制が背景にあるケースも考慮しなければなりません。違反が判明した際には、本人への指導に加え、上司の関与についても調査を行い、組織全体で問題解決に取り組む姿勢が重要です。
まとめ
従業員の勤怠管理は、企業にとって法令遵守の重要な責務です。労働時間や休憩、有給休暇などの関連法規を正しく理解し、各職場の実情に即したルールづくりを行うことが求められます。勤怠管理システムを活用して効率的に法令遵守を進める際には、「タッチオンタイム(Touch On Time)」の導入をぜひご検討ください。
「タッチオンタイム(Touch On Time)」は、株式会社デジジャパンが提供する、市場シェアNo.1※の勤怠管理システムです。専属のサポート担当がついており、追加費用なしで電話サポートが利用できます。あらゆる職場にフィットする独自のタイムレコーダー(TOTレコーダー、Facee)で、労働条件に影響されることなく打刻が可能です。
※2023年 富士キメラ総研調べ 勤怠管理SaaS市場 利用ID数
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
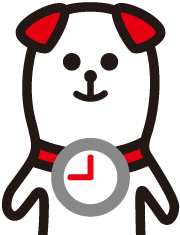
- この記事の執筆者
- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
- 受賞歴:「BOXIL SaaS AWARD Spring 2025」勤怠管理システム部門
ITトレンド Good Productバッジ 2022