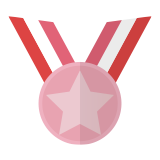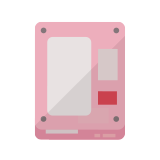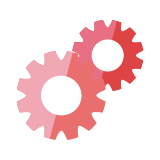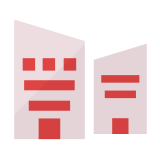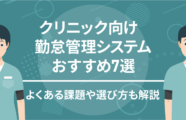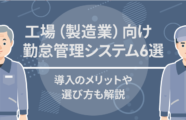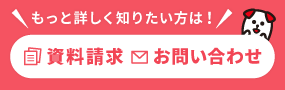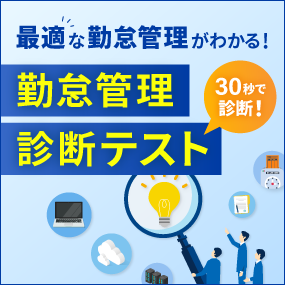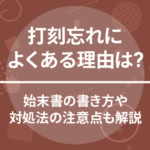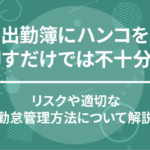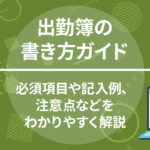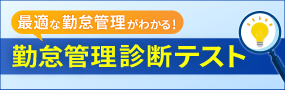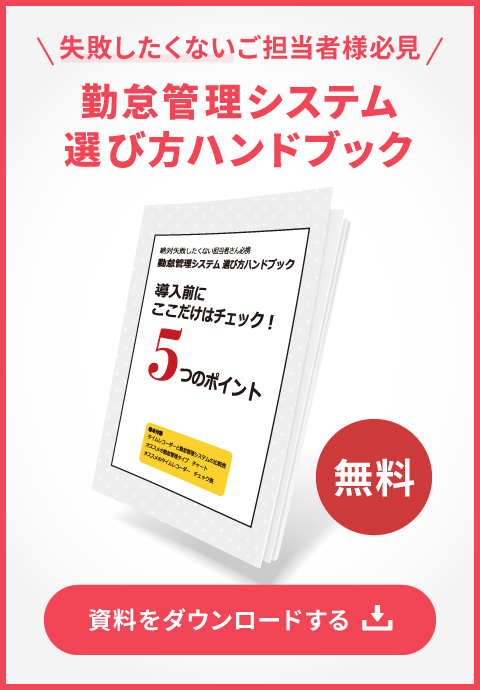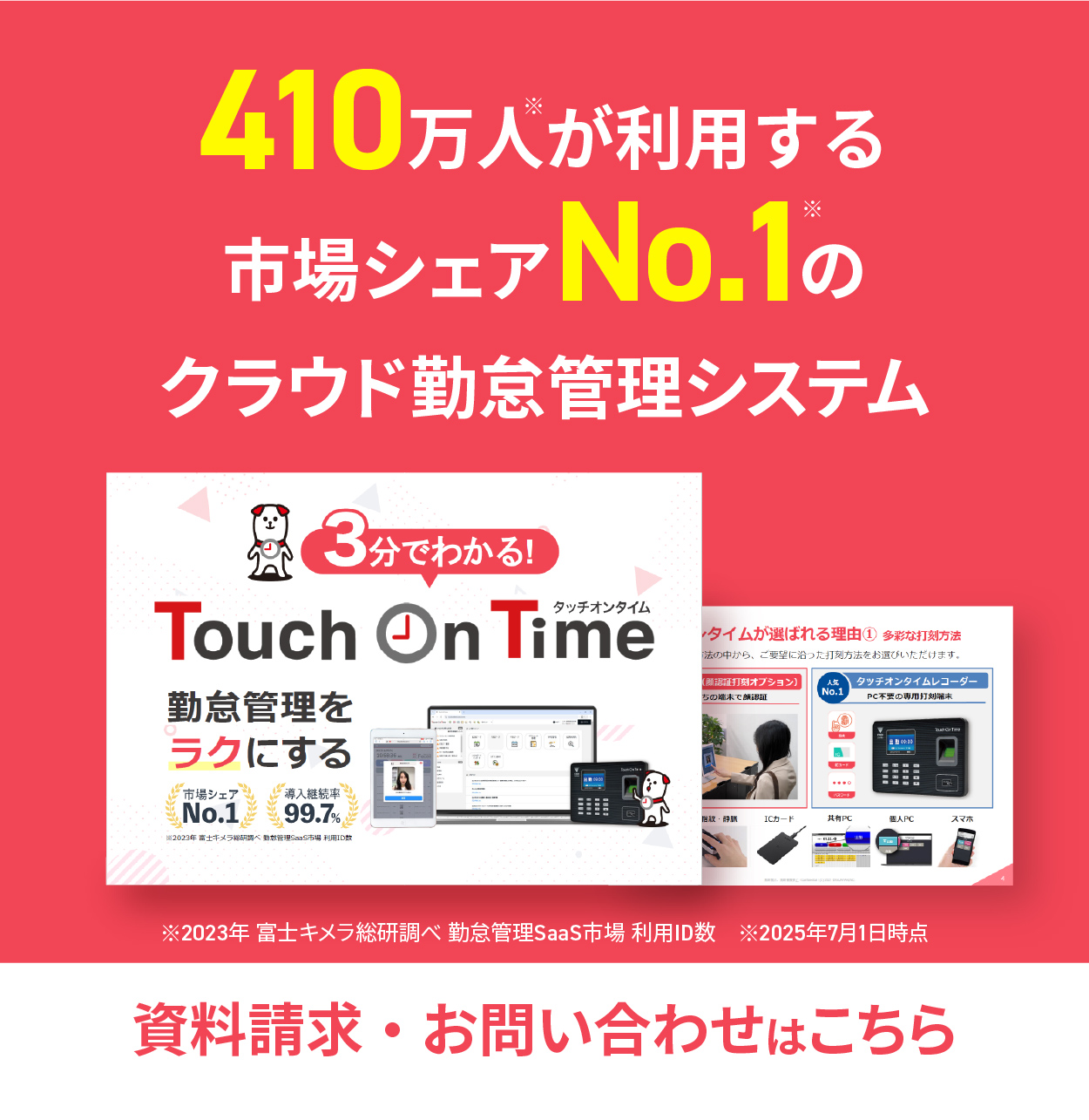タイムカードの押し忘れを放置するリスクとは?正しい対処法も解説
勤怠管理システム
打刻
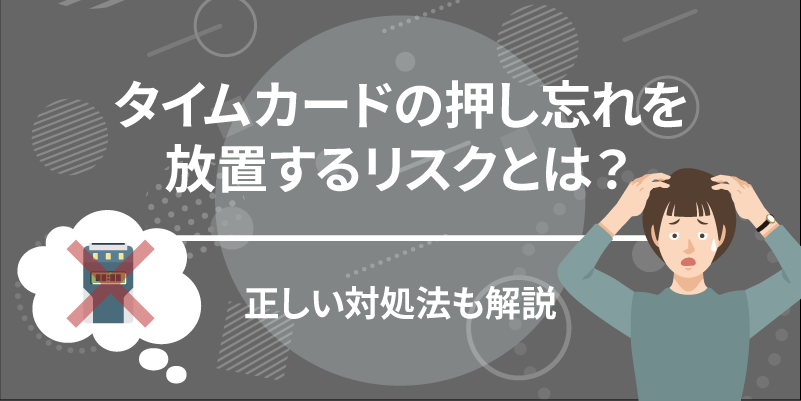
公開日:2025年9月19日
こんにちは。シェアNo.1クラウド勤怠管理システム「タッチオンタイム」のコラムチームです。
従業員のタイムカードの押し忘れを放置することは、企業にとってさまざまなリスクになります。本記事では、押し忘れをそのままにするリスクや、発覚したときの正しい対処法を解説します。
従業員がタイムカードを押し忘れてしまう原因や、押し忘れを防ぐ方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- タイムカードの押し忘れを放置することで起こるリスク
- 従業員が打刻を忘れる原因とよくあるパターン
- 押し忘れが発覚したときの正しい対処法と注意点
- 押し忘れを防ぐ具体的な仕組みやシステム導入の効果
目次
タイムカードの押し忘れを放置するリスク
タイムカードの押し忘れを放置すると、以下のようなリスクが懸念されます。
給与や残業代の未払いが生じる
労働基準法第24条により、企業は従業員に対して給与を全額支払わなければならないと定められています。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
しかし、タイムカードの押し忘れがあり打刻データが不足している状態では、正確な給与計算は困難です。その結果、給与や残業代の未払いが発生し、法律に抵触するリスクが高まってしまいます。
労働者には未払いの給与を過去3年にさかのぼって請求する権利があり、突然高額な支払いを求められる恐れもあります。
労働時間や残業時間を正確に把握できない
タイムカードの押し忘れを放置していると、従業員の労働時間や残業時間を正確に把握することができません。
労働基準法第32条により、従業員の労働時間は1日8時間・週40時間までと定められています。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
また、これを超える時間外労働に対しても上限規制が設けられており、特別な事情がない限り、月45時間・年360時間を超える時間外労働は認められていません。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条
➃前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
タイムカードの押し忘れにより打刻データが不足していると、知らず知らずのうちに上記の上限ラインを超過する危険性が高まるため注意が必要です。
労務トラブルに発展する
正確な労働時間の把握や給与計算が困難になると、従業員との労務トラブルに発展する恐れがあります。給与や残業代の未払いだけでなく、長時間労働により従業員の健康が損なわれた場合には損害賠償を請求されかねません。
たとえ従業員の押し忘れが原因であっても、正確な勤怠データがない状態を放置することは企業にとって大きなリスクです。
人事労務担当者の負担が増える
タイムカードの押し忘れが発生すると、人事労務担当者は正確な勤怠データを確定させるための作業に追われることになります。場合によっては、監視カメラや入館記録などのチェックも必要です。
押し忘れがあるたびにこのような作業を繰り返していると、担当者の負担が増大し、本来の業務に割けるリソースが減少してしまいます。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
従業員がタイムカードを押し忘れる原因
なぜタイムカードの押し忘れが発生してしまうのか、よくある4つの原因をまとめました。
タイムレコーダーの場所に問題がある
タイムレコーダーが出入口から離れた場所に設置されていたり、目につかない場所にあったりすると、従業員が打刻を忘れる可能性が高まります。同様に、タイムレコーダーの目の前に荷物や事務用品などが置かれていると、従業員の視界に入りづらくなります。
また、タイムレコーダーの近くにトイレや休憩室などがあることも原因のひとつです。従業員がそれらの設備を利用したあとに、そのまま打刻を忘れてしまう場合があります。
打刻に手間がかかる
タイムカードの打刻に手間がかかると、押し忘れにつながりやすくなります。特に、始業・終業間際で急いでいるときや忙しいときなどには、手間のかかる作業を後回しにする心理が働き、そのまま打刻を忘れてしまう恐れがあるでしょう。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 打刻のためになにかを取り出す必要がある
- ワンステップで打刻ができない
- 自分で時刻を入力する必要がある など
仕事に意識を持っていかれてしまう
出社時や退社時に、その日の仕事の内容や段取りで頭がいっぱいになり、タイムカードの存在を忘れてしまうケースもあるでしょう。特に、始業前は仕事の準備があるため、押し忘れが起こりやすいといわれています。
打刻の習慣が定着していない
入社後間もない従業員による押し忘れは、打刻の習慣が定着していないことが原因と考えられます。この場合は、始業後・終業後のルーティンが身につけば、自然と打刻を習慣化できる可能性が高いです。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
タイムカードの押し忘れに対応するときのポイント
タイムカードの押し忘れが発覚した場合は、次の4つのポイントを押さえて対応しましょう。
欠勤扱いはNG
タイムカードの押し忘れが発覚しても、その従業員を欠勤扱いとしてはなりません。出社して労働したという事実があるにもかかわらず、タイムカードの押し忘れを無給として扱うと労働基準法第24条や労働契約法第6条の違反となります。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
(労働契約の成立)
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
※引用:労働契約法|e-Gov法令検索
また、労働安全衛生法第66条の8の3により、企業は従業員の労働時間を把握しなければならないと定められています。
第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
従業員による押し忘れがあっても、労働時間の把握は企業の義務であると考えられるため、無給扱いとするのは適切ではありません。
従業員に確認し、打刻データを修正する
タイムカードの押し忘れが発覚したら、当該従業員に確認のうえ打刻データを修正しましょう。その際、必要に応じてパソコンのログイン履歴やオフィスの入退館記録などを確認し、情報の正確性を担保することが大切です。
手書きで修正する場合の注意点
紙のタイムカードの場合、打刻時刻の修正は手書きとなる場合が多いでしょう。手書きの勤怠記録は不正や改ざんが容易なため、トラブルを未然に防ぐためにも修正前の記録を残しておくと安心です。
また、従業員がタイムカードを修正したあとは、必ず上長が内容を確認するようにしましょう。
押し忘れの理由をヒアリングする
タイムカードの押し忘れがあったときは、従業員に理由を聞くようにしましょう。企業側に原因があった場合、事情を聞かずに一方的に対処すると、トラブルに発展するリスクが高まります。また、従業員に適切な指導をするためにもヒアリングは重要です。
できるだけ素早く対応する
タイムカードの押し忘れに対しては、できるだけ素早く対応することが大切です。時間が経つと関係者の記憶が曖昧になり、正確な労働時間の把握が困難になります。
また、管理者側が素早く対処できるようにするため、従業員には押し忘れに気づいたら即座に報告するよう周知しましょう。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
タイムカードの押し忘れにペナルティを課すことは可能?
タイムカードの押し忘れが何度も続くなど、場合によっては従業員への処分を検討するケースもあるでしょう。法律に抵触しない範囲であれば、押し忘れに対してペナルティを課すことは可能です。ここでは押し忘れが「合法となる場合」と「違法となる場合」の対処法や注意点を解説します。
合法となる場合
あらかじめ就業規則で定められている場合は、タイムカードの押し忘れに対して懲戒処分を課すことも可能です。また、同様に就業規則に規定があれば、始末書の作成を命じることもできます。
ただし、懲戒処分を下すためには、客観的合理性と社会通念上の相当性が必要です。例えば、うっかり何度かタイムカードを押し忘れただけで減給とするのは「罰として重すぎる」と判断され、裁判で無効になる可能性があります。
そのほか、人事評価に反映する方法もありますが、その場合も妥当性があるか十分に検討する必要があります。
減給する場合は法律の上限に注意する
労働基準法第91条では、減給処分を課す場合の金額について以下のとおり定められています。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
例えば、従業員の1日の平均賃金が20,000円の場合、10,000円を超える金額を減給してはなりません。懲戒処分としての減給が認められるようなケースでも、上限を超える減給は違法となるため注意が必要です。
違法となる場合
前述のとおり、タイムカードの押し忘れを欠勤扱いとして無給にすることは、複数の労働関連法に違反する恐れがあります。また、労働基準法第16条では「企業は労働契約において、違約金や賠償金の支払いを約束させてはならない」と定められています。
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
例えば、タイムカードの押し忘れに対して罰金を課すことは、上記の規定に違反する可能性が高いといえます。就業規則に無給扱いや罰金についての記載があっても、そのペナルティは無効となるため注意が必要です。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
タイムカードの押し忘れを防止する方法
タイムカードの押し忘れを防ぐためには、以下のような対策を講じることが大切です。
出退勤の動線上に設置する
従業員の出退勤の動線上にタイムレコーダーを設置すれば、タイムカードの押し忘れを防ぎやすくなります。デスクやスケジュールボードの近くなど、従業員が必ず通る場所や、目に入りやすい位置に設置しましょう。
事業所としての規模が大きい場合は、タイムレコーダーを分散して設置するのがおすすめです。十分な量のタイムレコーダーを設置することで、打刻のための行列も防ぎやすくなります。
リマインドツールを導入する
従業員の出退勤時刻がほぼ固定化されている場合は、リマインドツールを導入するとよいでしょう。「従業員は打刻を忘れることもある」という前提で仕組みをつくることが大切です。
具体的には、ビジネスツールのリマインダー機能を活用したり、始業・終業時刻にアナウンスを流したりする方法があります。
正確な打刻の重要性を周知する
タイムカードの押し忘れを防ぐためには、従業員への意識づけを強化することも重要です。押し忘れは誤った勤怠管理や給与計算の原因となり、従業員自身にもデメリットがあります。
正確な打刻は労働者側にとっても重要であることを周知し、打刻の意識を高められるようアプローチしましょう。
勤怠管理システムを導入する
タイムカードの押し忘れがなかなか減らない場合は、勤怠管理システムの導入も検討してみましょう。
パソコンやスマートフォン、ICカードなどの多様な打刻方法を利用できるため、従業員が柔軟に打刻できる体制を構築できます。製品によってはアラート機能が搭載されており、押し忘れを効果的に防ぐことが可能です。打刻データの修正もスムーズにできるため、万が一押し忘れがあった場合も安心です。
また、労働時間や残業時間などが自動集計されるため、集計作業の手間やミスを軽減できるのもメリットです。給与計算システムや人事システムなどと連携すれば、人事労務業務全体を効率化できます。
勤怠管理のお悩み解決なら!タッチオンタイム
まとめ
タイムカードの押し忘れを放置すると、勤怠管理や給与計算の正確性を担保しにくくなります。従業員との労務トラブルに発展するリスクもあるため、適切に対処することが大切です。
勤怠管理システムを導入するなら、「タッチオンタイム(Touch On Time)」をご検討ください。株式会社デジジャパンが提供するタッチオンタイムは、市場シェアNo.1※の勤怠管理システムです。
さまざまな労働環境でも打刻環境を整えられるよう、タイムレコーダーを自社開発しており、指紋とICカード打刻が可能な独立型端末「タッチオンタイムレコーダー」やお手持ちの端末で利用できる顔認証打刻「Facee(フェイシ―)」を提供しており、労働条件にかかわらず柔軟な打刻が可能です。
初期費用0円で月額費用は1人300円と、低コストで豊富な機能をご利用いただけます。専属担当による電話サポートはもちろん、全ての機能を追加費用なしで利用できます。まずはお気軽にお問い合わせください。
※2023年 富士キメラ総研調べ 勤怠管理SaaS市場 利用ID数
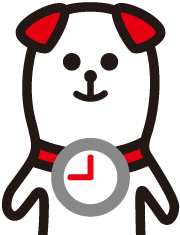
- この記事の執筆者
- 株式会社デジジャパン「タッチオンタイム」コラムチーム
- 受賞歴:「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」勤怠管理システム部門
ITトレンド Good Productバッジ 2022